おとなでも 子どもでもなかった頃の 私と王子くんに。
二年生への進級というのは、代わり映えのしないものだと思う。緊張しきっている新入生とも、大学受験を控えている三年生とも違う。ただ、無感動に進級を享受するだけの学年。クラス替えには多少ドギマギもするものだが、この学校では二年生で進路志望別の授業に別れるのだから、ある程度クラスメイトの予測も出来る。一年生のときのクラスに一度集合させられ、新しいクラスの名簿をそれぞれに配られた時、ざっと新たなクラスメイトのメンバーを眺めて、予想通りさにため息をついたのだった。そっと窓の外、桜が咲いているのが目に入る。平年より開花が早めだったせいなのか、今にも零れそうなほどの咲き誇り方。桜は毎年咲くけれど、飽きないうつくしさだと思う。はかなさ、というのがやはり日本人の心に響くのかもしれない。
私が二階の窓から見下ろせる校庭の木々に気を取られているうちに、教師が諸連絡を言い終わっていた。ようやく解散となったときには、なんだかんだ言いつつも少しは抱いていた新しい学年への期待は既に失せていた。また選択授業でね、なんて言いながらさして仲良くもなかったクラスメイトに別れを告げる。同じクラスに振り分けられた友人は私がモタモタしている間に、先に教室に向かってしまったらしい。相変わらず冷たいこと。私の友人はどうにも冷たい人が多い気がする。
一年生のときはG組だった私だけれど、新学年ではC組だ。アルファベットは良く似ているのに、教室はほとんど端と端みたいなものだ。それはちょっと言い過ぎかもしれないが、とにかく教室移動のために廊下を歩いていた。A組からH組まで横長の校舎に一列で順に教室が並んでいる。階段は中央と両端の三つあり、C組の教室は真ん中の階段よりひとつ向こうの教室だ。向かいには渡り廊下があり、そこから理科室や図書室、職員室等がある特別教室棟へと続いている。騒がしくなるかもしれないな、と少しげんなりしながら教室へ入ろうとした。
代わり映えはしないといえ、今日から新たな学年だ。緊張感はそれなりにある。良くも悪くもこの最初の一日で一年が決まる、というのは少し構え過ぎか。小さく深呼吸をして閉まっている後ろの扉に手を掛けた時、声を掛けられた。「あの、すみません」男子にしては少し高めだろうか。透き通った声は不愉快ではない。それでも心当たりのない声に少し眉をひそめながら振り返った。
男の子がいた。ネクタイの色を見る限り同じ学年だろう、その男子生徒は一年通っているには真新しい、ピリッと糊のきいたブレザーを着込んでいた。まだ春なのに、縦縞のマフラーも巻いている。それが男の子の、すごく現実離れした空気を作り出していたのかもしれない。「H組って、どこの教室ですか?」緊張しているのか、同学年なのに堅苦しく敬語で尋ねてきた彼に、私はそっと今来た方向を指差す。
「あっちだよ、一番向こう」
「ありがとう」
丁寧にお礼を言って、にこりと笑ったその男の子は、なんていうか、可愛かった。去っていく後ろ姿、日本人離れしているなあ、と思った理由は髪の毛の色だろうか。染めた様子のない茶髪ーー榛(はしばみ)色というべきか、とにもかくにも黄色掛かった茶色の髪の毛がふわりと風に吹かれていた。そういえば、女の子みたいに大きくて潤んだ瞳も、同じような色だったっけか。
学年全員を覚えている訳じゃないけれど、見たことの無いその子。もしかしたら転校生かもしれないなあ、なんて思いながら、高校で転校なんてそれも現実的じゃないかなんて自分で否定して、教室の中に入っていった。先ほどまで抱いていた緊張は疾(と)うにどこかへ行ってしまっていた。

その子のことを考えていたのなんて、ほんの一瞬。すっかり忘れ去ってしまってから、およそ半年経った十月のこと。意外な所で彼と再会することになる。所属していた図書委員会。前期後期の入れ替えとともに、新たなメンバーでの活動が始まった。通年の委員ではないから、前期から比べるとだいぶ顔触れが変わったなあ、と思ったがさして興味は持てなかった。関わる人と言えば本当にごくごく一部だからだ。当番決めと簡単な掃除で、初回の委員会が終わる。あとはそれぞれの当番に行けばいい。正式な委員会活動は、しばらくない。
後期に切り替わって最初の金曜日。見慣れないーー否、どこかで見たことのある男の子がすでにカウンターの中に座っていた。室内にいるのに、しかもまだ十月なのに、縦縞のマフラーを巻いている。寒がりなのだろうか。否、前に見かけたときも彼は同じマフラーを巻いていたはずだ。ゲンを担いでいるのかもしれない。ともかく、おや。と、そう思いつつ、空いていた彼の隣に腰掛けると、彼はこちらを振り向いた。
「金曜日放課後の当番の子だよね、半年よろしく」挨拶がてらそう言いつつ、ついでに自分の名前を告げると、彼はきょとんとこちらを見たあと、納得したように頷いた。
「フータ・デッレ・ステッレ」
相変わらず柔らかく透き通った声だと思った。きらきらと星のように輝くうるんだ瞳とかち合う。なんとなく、彼に似合いそうな愛称を思い付きそうだと思ったけど、それは何処かに飛んでしまう。それよりも、彼が何を言ったのかがよくわからなくて、首を傾げて暗に意味を問う。
「名前だよ。みんなはフゥ太って呼んでるから、そう呼んでくれると嬉しいな」
にっこりと笑って、窺うように首を傾げると、やわらかそうな髪の毛がふわりと宙に舞う。基本的に茶髪は禁止されているのに、やはり地毛だったからだろう、二年生の最初の日と同じ榛色のままだ。それがさらにふわふわとした印象を醸し出している。
「僕、委員会とか初めてなんだけど、何をやれば良いのかな」
「んー、委員長がこないだ説明してたように、基本は貸し出し返却の作業だよ。そもそもうちの学校、図書室の利用者少ないから、人がいないときはなにやってても良いの」
「宿題でも?」
「もちろん。本を読んでても良いし、ぼーっとしてても。あ、でもケータイ触るのはだめだよ」
「そもそも持ち込みが許可されてないよね」
彼の尤もな言葉に、笑って誤摩化した。持ち込み禁止は表立って使わなければ暗黙の了解でなかったことになってるし、目立つ行動をしなければ教師も没収なんてしない。それをわかってしまっている二年生の大半は、持ってきているものなんだけれど。そこで思い出した。H組に転校生が来たって話。十九八九この子のことだろう。外見だけでなく、名前もどこか西洋染みてるし。
「どこから転校してきたの?」
「僕、学校行ってなかったんだよね」
秘密だよ、と女の子が好きそうな感じに悪戯っぽく笑って、彼は片目を閉じた。そのやさしい薄茶色の瞳が隠されてしまうのが何だか勿体ないなって思った。「出身はイタリア」私の疑問に答えるかのように言ったその子は、鞄の中から青いチャート式を取り出した。宿題をやるつもりなのかな。そう思って、私は自分も本を開く。さして親しくもないし、話題も無いのだからこれ以上、話を続ける理由が無かったからだ。ページを捲(めく)るスピードはいつもと同じだったけれど、隣が気になって頭の中に内容は余り入ってこなかった。

数週間が経った。私と彼の距離は、縮まることも無く、隣でいつも別々の作業をしていた。けれど週に一度、金曜日の放課後、そこに行けば彼に会えるということが、私をわくわくさせていたのも事実だった。彼と特別親しくなった訳ではない。けれど、彼の空気が好きだった。学校にいる、男の子達とはちょっと違う感性。何かを憂いているような雰囲気。うるうるとした瞳が時折、無感情に色を消す。その刹那、なにかどきりとするものがあるのだ。当番の初めと終わり、二、三交わす言葉が私にとって特別なものになるのに、そう時間はかからなかった。
何を悩んでいるのか、何故マフラーを付けているのか、どうして日本に居るのか。いままで学校に通ってなかったのに、なぜ急に転校してきたのか。聞きたいことは山ほどあったけど、それをぶつける勇気は出ずに、私はいつものように本を取り出す。
今日持ってきた本は、ほんとはもう既にほとんど読み終わっていた。十分か、二十分か。たぶんそれくらいで読み終わって、ふと顔を上げると、まだ外は明るかった。窓の外から、運動部の子達が元気に叫ぶ声とか、吹奏楽部のクラリネットの音が入り込んで来る他は、とても静かだった。隣を見ると、いつもとは違い、宿題をやっている訳ではなかった。とても大きな本の表紙を、開(ひら)かずにじっと眺めていた。それがまるで命よりも大切なように見つめていた。
それがとても危うくて、私はノートに走り書きをする。先ほど読んでいた、『星の王子さま』に出てくる、有名な形だ。「これなーんだ」彼の思考を邪魔するようにスっと、その本の上に差し入れ、彼に聞く。ぼんやりとしていた彼は、そっと現実に魂を呼び戻すように、その薄茶色の瞳に色を宿し、数秒見つめる。そして私の方を見ると、いつものように首を傾げつつ「なんだっけ、ゾウを飲み込んだヘビだっけ?」思いのほか平静な声で答えた。
私はなんだかがっかりしつつも、イタリア出身ならやっぱり知ってるだろうなって思った。こんな遠い島国でさえこんなにも有名な作品なんだから、お隣の国の人が知らないはずが無いだろう。「読んだことあるんだね」「お兄ちゃんみたいな人が、僕にぴったりだよって、毎晩読んでくれたことがあってね」彼の家庭事情に少しだけ触れてしまった感じに、どぎまぎしながら、「でもさ、」なんて言って、私は走り書きに手を加える。

「これ、こうするとなんかカタツムリに見えない?」
「きみって、変なこと考えるね」
ばかにされているような台詞だけれど、その意図はあまり感じられなかった。面白そうにその大きな瞳を目を細め、彼は私を見た。何を言っていたのか困って、私は思ったままに呟いた。「いつも思うの、薔薇に四本のトゲではなく、翼があったらって」「ほんとに、変なことを考えるんだね」どうしてか、悲しそうな表情をしたと思ったら、彼は「僕、昔ね、いろんなおとなのひとに『星の王子』って呼ばれてたんだ」重要なことのように、秘密を漏らすように囁いた。「……」私は何を言っていいか分からない。でも、彼はそんなこと気にしていないようだった。なにか大切なもののように、カウンターに置いていた大きな本をぎゅっと抱きしめる。
「僕は学校に通ってなかったって言ったよね。情報屋だった。ランキング能力があったんだ、正確にねいろんなことのランキング付けが出来るっていう。これが無くなったのに、僕は本当にツナ兄の傍に居ていいのかな。教育係の役目も終わってしまった。僕は、足手まといじゃないのかな」
「んー、よくわからないけど、私、順位付けってすきじゃないけどな」
「僕は、ツナ兄の役に立ちたいんだよ。ねえ、みょうじさん。僕は、ランキング能力を取り戻したい」
彼の言っていることは正直、よくわからなかった。こちらの想像を超えることを、聞き手の様子など気にしないで呟いている様子が、なんだか本当に王子さまのようだなと思った。それに、彼の言っている内容よりも、彼が私の名字を口にしたことの方が私にとっては重要だった。自己紹介して以来、一度も呼ばれなかった名前。覚えていたのだと不意に思い知らされて、なんとなく嬉しい気持ちにさせられる。そうか、私は彼にきちんと認識されていたのか。
「それなら、私がきみの花になってあげよっか」
「えっ?」
「ああ、違う。望むなら協力してあげようってこと。ま、私は何にも出来ないけどさ」
王子さまの大切にしていた薔薇のようになれたらいいのに、と思ったけれど、それはわたしの独りよがりだ。ましてや自己申請するものじゃない。思わず零れ出た本音を誤摩化して、上書きした。きっと、彼はこんなこと望んでなかったんだと思う。ううん、おそらく考えてすら居なかったんだ。その証拠のように、大きな目をさらに見開いてきょとんとしている彼。
「もっと教えてよ。ね、子どもだった頃、きみはどうやってランキングしてたの?」
彼が話してくれたことで気が緩んでいたんだと思う、思わずそう尋ねると、彼はちょっと困ったように微笑んだ。控えめな笑みに、やってしまったかと自分を責めるが届いてしまった言葉は撤回出来ない。やっぱりいい、なんて今更言えないで、気まずい空気がカウンターに充満した。それでもいくらかして、彼は何かを言おうと口を開いてーータイミング悪く滅多に来ない利用客がやってきて、私達は会話を中断せざるを得なかった。
「二週間の貸し出しなので、再来週の金曜日までになります。延滞しないように気をつけてくださいね」
内心少しほっとしながらも、定例のようにそう言った。利用者は他に特に何も用件はなかったらしく、貸し出し処理を済ませると、すぐに図書室を去って行った。どうしようかと思って、隣に座る彼を見やったとき、再び私達の間は遮られる。
「みょうじさん、フゥ太くん。今日は先生、少し用事があるから早めに閉めるね。片付けて、帰って良いわよ」
裏の司書室から、カウンターに顔を出した司書の先生だった。タイミングが悪いな、と思いつつもこれでよかったのかもしれないという思いはぬぐい去れなかった。たぶん、これでよかったのだ。これ以上踏み込んだら、彼とこうやって会話することはできなくなるかもしれない。変に彼のことを知るよりも、金曜日の放課後、決まった時間に彼に会えることの方が大切だった。木曜日にちょっとどきどきし、金曜日になると胸が高鳴って、そして放課後に近付くと、頬が色づきそうになるーーこの感覚をここしばらくの間、誰にも言わず密やかに楽しんでいたのだから。仲良くなるということは、別れのつらさがあるということ。私は完全に失念していたのです。
先生に挨拶をして手早く荷物をまとめると、私は逃げるようにその場を立った。あまりの素早さに相方の彼が目を瞬かせているうちに、私は気まずい空間から立ち去りたかったのだ。
「待って!」
大きな声で叫ばれて、手首を掴まれて、私はびっくりした。もう閉館で、利用者が居なかったのが唯一の救いだろう。びくり、と全身を振るわせると、彼はしまった、という表情で私を見つめる。
「ごめん、驚かせるつもりはなかったんだよ。ねぇ、今から時間ある?」
「どうして?」
「ランキング、見せてあげる」
えっ。使えなくなったんじゃなかったのか。どういう風の吹き回しで? 訳が分からないまま、彼のやわらかい瞳を見つめ返すと、彼は神妙な面持ちのまま頷いた。「僕が使えなくなった、ランキングだよ。子どもだった頃と同じように、やってみよう」あまりにも真剣だったものだから、私は怖くなった。彼の視線から逃れるように、窓の外を見やるともう日は沈み始めていた。日の入りは、たしか王子さまが一番好きだった景色だ。寂しくなると、見たくなるんだと言っていたっけ。この地球では寂しくなったときに、椅子を動かせば見えるものでもない。一日、二十四時間に一度だけの景色。なんだか、それが貴重なもののように思えた。私の手首を掴んでいる彼の、やさしい黄色掛かった薄茶色が夕焼けのあかに溶けていく。消えてしまいそうだと思った。久しぶりに、彼が儚い雰囲気を纏う男の子だと意識した。
「お母さんに、遅くなるって電話してくるね」
断ることを、考えもつかなかった。先に昇降口へ行くと言って降りて行った彼を見送ると、電話を掛ける。予想通り良い顔をしない母親を説き伏せて、私は走って下足箱へ向かった。ローファーに履き替えると、丁度昇降口を出た所に彼を見付ける。沈みかけた赤い日差しに溶けかけている青年。ああ、私はもしかしたら、本当は出逢うはずも無かった人と話しているのかもしれない。そんな錯覚に陥る。
「フゥ太くん!」
名前を呼べば、彼を現実に引き戻せるような気がして、思わず叫んでいた。ぼんやりと日の入りを眺めていた男子生徒は、驚いたようにこちらを見る。
「みょうじさん、僕の名前覚えてたんだね」
「案外、失礼だね、きみって」
「あ、ごめん」
「いいよ、私もさっきまで同じこと思ってた」
うるっと瞳を潤ませて謝った彼は、私が同じことを告白すると、ちょっとむくれたように口元を膨らませた。似合うと分かっててやっているのだろうな。本当に、それが様になるのだから羨ましい。他の男子がやっていたら気持ち悪いだけだろうに。これも、また彼が現実離れしているのを私に思い知らす。
「で、何処で見せてくれるの?」
「住んでる所の近くに、公園があるんだ。そこでいいかな」
「ん……。きみの住んでる所ってここから遠いの?」
「近いよ。ずっと、並盛に住んでるから」
意外だなって思った。ずっと、並盛に住んでいるなんて。私の家も、そう遠くないせいか、彼がこの近くに住んでいることが何やら不思議でたまらなかった。いつから住んでいるのだろう。私は、彼について知らないことだらけだ。
「ほら、ここ」
子ども達が遊ぶような、ちいさな公園だった。砂場に、ブランコと滑り台、あといくつか遊具がある程度の、市街地のほんの小さな公園。時間も時間だからか、人っ子一人いなくて静まり返っている。道中で子どもの声はしたのだから、きっと今は帰り道なのだろう。懐かしいな、なんて言いながらザクザクと足を踏み入れて行くその姿は、なんだか遠いもののよう。
置いて行かれたくなくて小走りで彼に追いつく。隣に並ぶ勇気はなくて、影の頭が並ぶ程度の距離、斜め後ろに立つ。彼は公園の真ん中に立つとこちらを振り向いた。二人して、立ったまま見つめ合う。それが刹那だったのか、数分だったのかはわからない。彼がそっと口を開いた頃には、気が付けばもう辺りはすっかり暗くなっていた。
「何が起こっても、何が起こらなくても、驚かないでね」
緊張した声色で、彼は言った。喉が渇いているのか、少し掠れている。その所為でいつもより低めの声が心地よかった。もっと聞いていたいと思ったけれど、本題はそれじゃない。私は、こくりと頷くだけ。黙ったまま彼を見つめていた。
「こちらフゥ太、聞こえるかい……ランキングの星」
どこぞのファンタジーのよう。
彼は何かを怖がるようにそっと目を瞑って、そう呟いたかと思うと、決意を込めた様子で瞼を開いた。きらきらとした瞳。まるで、この夜空に輝いている星々がそのまま瞳の中に吸い込まれたようだった。ここまで生き生きとした彼を見るのは初めてで、面食らってしまった。
驚くのはそれだけではなかった。なんでもなかった周囲がふわりと重力に逆らい始める。公園の砂粒や小石、それから枯れ葉とかいったものがふわりと浮き上がる。彼のふわふわの茶髪も、トレードマークの縦縞のマフラーも例外じゃない。ふわふわと、浮かび上がって、非現実的な今を作り出す。私の髪の毛も宙で踊っていた。摩訶不思議だった。
(夢でも見ているのではないか)
そう思ってしまうのも道理だろう。これから何が起こるのか、すこしわくわくとしていたところ、突然彼が顔を歪めたかと思うと、今まで見ていた景色は消え去った。浮いていたものは自然に元通り。残ったのは、顔を歪めて悲しそうにその場にうずくまった彼が一人。
距離を取っていたのも忘れ私は近寄った。「フゥ太くん」意味が無いとわかっていつつ、名前を呼ぶ。「かなしいんだ」彼はそれだけをぽつりと零して、ぎゅっと歯を食いしばったようだった。ぎりり、という音が聞こえてきそうだった。「名前を呼んで」「フゥ太くん?」「フゥ太って」消えてしまいそうな男の子を前に、どうしてこんなに大胆な行動がとれたのか、今の私にもわからない。彼を慰めるように、いつくしむように、そっとぎゅっと抱きしめた。「フゥ太。ね、だいじょうぶだから」私の言葉は彼に届いたのだろうか。しばらくそうしていたけれど、「ごめん、ありがとう」彼のその言葉を聞くと、私は離れる。
最初に保っていたのと同じ距離を取ると私はそこに座り込んだ。制服の襞(ひだ)スカートがよごれてしまうのも構わない。「冷えるよ」「きみに言われたくない」気を使ってくれていたのだとは知っていたが、にべもなく流すと、彼はまたむくれたように頬を膨らませた。
「もう、こうやって会えなくなるね」
「……どうして?」
「だって、もうすぐ委員会、終わりじゃない」
私の言葉に、息を殺すように聞き返した彼に対してあっさりと答えると、困ったように笑って、そうだねって。まるで、それが理由じゃないみたいに。私は私で、別れの気配を読み取っていたのかもしれない。「他に何があるの」なんて冗談めかして笑いつつも、そっと空を見上げた。すっかり日は沈んでしまい、きらきらと星柄の黒いベールが天井を包む。月も出ていないから、余計に星が輝いていた。せめて周囲の電光さえなければ、もっと綺麗に見れただろうものを。
「僕は、知らない間に大人に近付いてたんだなあ、って思ったよ」
地面に手を付き、私と同じように空を眺めている彼は言った。「きっとお別れだね」それが、委員会の終わりを告げる口調じゃないことくらい、そろそろ分かり始めていた。「きみのおかげだ」なんて言葉も、聞きたくなかった。踏み込まない踏み込まないと思っていたけれど、こんなに離れがたくなる程度には踏み込んでいたのだ。離れたくないから知りたくない、そう思ってしまった時点で、もう手遅れなのに。毎週金曜日の放課後、そのどきどきとわくわくを壊したくなかった。子どもみたいに、涙が零れた。彼はそれを見付けて、はっとしたようにこちらに近付いてくる。ごめんね、困らせるつもりじゃなかったの。つらいけど、つらくないよ。引き止めたいけど、引き止められないの。フゥ太、きみは自分の星に帰るのだろうから。
「わたし、来年の今日も再来年の今日も、ここで星を見るよ」
「雨でも?」
「雨でも」
「嵐でも?」
「嵐でも」
「晴れだったとしても?」
「もちろん。曇りで星が見えなくても、霧が出てたとしても、必ずここできみを思い出すから」
もしも、ここで箱の絵を走り書きしたとして、私も彼も、その中に『王子さま』の見たような羊を見ることはできないのだろう。ぼうしのようなあの絵の中に、象とヘビが見れなかったのと同じように。でも、あれがカタツムリのようだと思った私なら、もしかしたら違うものが見れるかもしれない。
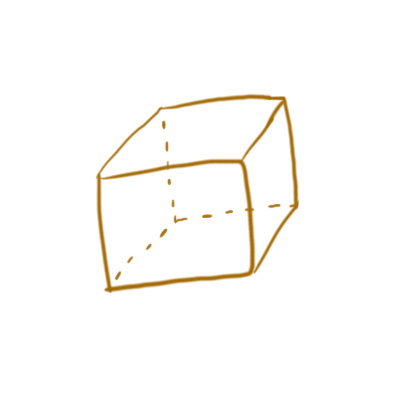
木の枝を拾って、地面に箱のような絵を描いた。私ときみを結ぶための指輪が入ってたらいいのに。そんなメルヘンチックなことは私は絶対に口にしないだろう。「君が望むものが、ここには入ってます」見える? って、つらいのを隠して悪戯っぽく尋ねると、彼はちょっと悩んで「そうだな」って言った。
「リングがあれば、きっとぼくだってランキング能力に頼らなくって良くなるかもしれない」
私の心を読み当てられたのかと思ったけど、そうでは無いみたいだった。でもそれでも、同じものを想像して、胸の中がじんわりするようなあたたかみに満たされた。ああ、嬉しい。嬉しい。離れたくない。かなしい。さびしい。心の中が、いろんな感情でぐっちゃぐちゃになっていて、どうしていいか分からない。それが表情に出ていたのか、彼は私の頭をくしゃくしゃと撫でた。首を傾げると「教育係をしてた、弟みたいな子がね、こうすると喜んだから」子ども扱いされているのだと恥ずかしく思ったけど、彼に触れられているのは嫌じゃなかったから、彼をまねて頬を膨らませるだけに留める。
「帰ろっか。送るよ」
「え、いいのに。自分で帰れるよ」
「僕がそうしたいんだからーーああ、あと。この本、預かっててくれない?」
図書室のカウンターで心底大事そうにしていた大きくて分厚い本を見せると、彼は頼み込むように瞳をうるませる。これを計算尽くでやっているのだと、もう理解(わか)っていないとは言えなかった。それでも、騙されるように私は頷く。
「貸し出しは、いつまで?」
「そうだな。僕が、オトナになるまで」
「長いね」
「その本を、僕が必要としなくなる時まで、持っていて欲しいんだよ」
吹っ切れた様子の彼は、激しくはない、けれど強い口調でそう言った。何で私なんだろう。疑問を抱くが、いつものように、尋ねることはしなかった。ただ、これを持っている限り私は、この王子くんを忘れることは出来ないのだろうと、漠然と思った。
私のペースに合わせてゆっくりと、歩いている彼の息づかいに耳を澄ませる。こうやって歩くのは最後かもしれない。最後なら、と思い切って手をつなぐ瞬間を窺っているうちに、そっと手が重なった。息を呑んで、自分よりも随分と高い位置にある顔を見上げると、彼はふんわりと微笑む。私も、それに釣られるようにして、自然と笑顔を作っていた。

預かった本はよくわからない言語で書かれていて、中身の気になった私は一晩中インターネットで検索をかけていた。きっとイタリア語だろうとあたりをつけ、連日徹夜で翻訳機能とにらめっこ。
週明けは当然のように、寝不足だった。ヒントだけでも貰おうと、H組の教室へ足を運ぶ。だけれど、彼の姿を探しても見当たらない。嫌な予感がした。否、そんな気はしていたのだ。それこそ、あの晩、あの時から。だから、家に帰って追われるように検索をしていたのだと。去年のクラスメイトを捕まえ、聞いてみても、要領を得ない返事ばかり。彼のことを認識はしているのに、あまり覚えていない風なのだ。
消えるように去ってしまった彼のこと。どう考えていいのか分からない。だけど、過ごした日々だけは本当だったと言えるだろう。月並みだけれど、信じるしか無いーーあの不思議な体験を。
きっと、あの日と同じ場所、毎年星空に彼を見ていれば、ひょっこり現れるに違いない。オトナになった彼が、ふんわりと微笑みながら、あの本を返してもらうために、私に会いにくるに決まっているのだから。
薔薇にはねがあればいいのに、そう思ったことはあったけれど、きっと私は薔薇にもなれなかった。再会を願い、空を見つめるだけの、ただの狐に過ぎないのかもしれない。
フゥ太がランキング能力を取り戻そうとするおはなし。
→ある魔女の手記(夏井トオテル/同テーマ作品)
2013.03.04. 執筆
2013.12.13. 掲載
2018.07.10. 再掲載