My Dear
ほんとうにきれいな瞳ね、とゼルダに言われるのが自分の唯一の存在証明といえることだった。
彼女はいつも些細なことまで良く気が付いて、その可憐な唇で褒めてくれる。
自分と、彼女には決して消すことの出来ない身分の差があるのに。
拝啓、左目に不自由したことの無いキミへ。
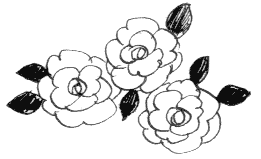
勇者リンクによって魔王ガノンドロフが滅ぼされ、このハイラルに平和がもたらされたのは、もうしばらく前のことになってしまう。連日、復旧作業に追われ、気が付いたらそんなに立っていたのかと暦を見て、シークはふと感傷に浸りそうになっていた。
ハイラルを救った時の勇者のことは、徐々に忘れられていき、今はあの男のことを詳細に覚えているのはごく一部だろう。忘却の呪いにでも掛かったかの様に、民から彼のことが抜けていった。緑の勇者は、魔王と共に滅んでしまった。その証拠に、何処からか現れたあの男は、もう、緑色の衣を纏っていなかった。もはや、勇者ではないのだ。
「おーい、シーク。そういえば、ゼルダが探してたみたいだよ」
出会い頭、軽い調子でリンクは唐突にそう伝えた。それを聞いたシークの反応は素早い。ほぼ完成している城壁に背を預け、昼食を取っていたシークは食事もそのままに立ち上がる。だが、それを苦笑いしながら制したリンクの言い分はこうだった。
「『昼食はきっちり摂ってもらってね』ってゼルダに釘を刺されたんだからな」
ほんっと、融通聞かないなあ、お前は。と言うのは彼に対するリンクの口癖みたいなものだ。シークも真面目な顔を崩さずに「姫がそう仰るのなら」と再び城の陰に座り込んで、手に持っていた食べかけのパンをかじる。
その隣に、自然な動作でリンクは腰掛けて、自分の昼食を取り出した。
リンクはシークやその他大勢の宮廷騎士達とは違い、王家に仕えている訳ではない。彼は誰にも忠誠を誓っていない。ただ、彼の持つ正義――ゼルダを守るという、ただそれだけのためにハイラルの復旧を気まぐれに手伝っていた。彼がやるべきこと、やりたいことは他にあるらしいが、それを口にすることは無い。シークとしても、特に危険視することはないと考えている。というのもリンクの、ゼルダに対するある種の異常な執着は、今のところ彼女を傷つける方向には向かないと判断出来るからだ。シークにとって、王家や国はさして問題ではない。ゼルダが無事ならば、それで構わない。
心の中でそれを再確認をした頃、ちょうど昼食も食べ終わる。シークは零れ落ちたパン屑を払い、無言で立ち上がった。リンクもそれを止める様子は無い。
「ま、がんばれよ」
その表情と口ぶりから、彼はゼルダの話の内容を知っているに違いないと踏んだ。そして、おそらくそれは間違っていないのだろう。
* * *
ゼルダはいつも通り、執務室にいた。
いつも通りシークがノックをして名乗ると、すぐに部屋の中から声が聞こえる。どうぞ、と促されて室内へ入る。彼女は既に書類から顔を上げていて、視線がかち合った。
呼びつけたことに軽く謝罪を入れ、シークが呼びつけられることこそが当たり前だと取りなすのは定例と化している。その後、ゼルダは柔らかく微笑んだあと表情を引き締め、シークへ向き直る。
「今回は他でもない、あなたにしか出来ないことを頼みに来たのです」
「……ゼルダが仰るなら」
真面目な表情、そして深刻な声色。ゼルダの言うことならば何でも引き受けると、決意を新たに小さく、しかしはっきりとした声でシークがそう言うと、彼女はコクリと頷いた。
ゼルダはシークが、彼女の頼みを、命令を断らないということを知っているのだ。それが、どういった類いのものだとしても、彼女に忠実であろうとするだろう。それが、彼女には哀しかった。シークが彼女のことを一番に考えるのなら、せめてシークに人並みの幸せになってもらいたい。シークに対するこの任務は、ゼルダのそういった私情と、王宮が求めている利益の両方を兼ね備えたものだった。
沈黙が支配する場。シークはいっさいの感情を外へ出そうとしていなかったが、内心は徐々に緊張してきた。必要とあらば、心を殺してでもなんでもシークへ命令していたゼルダが、ここまで焦らすのは初めてだった。
とうとう彼女は口を開く。うつくしく落ち着いたソプラノの声が、シークの耳へとその指令を運ぶ。
「シーク。二日後のこの時間、お見合いをなさい」
時間が止まった。
正確には、シークの思考が停止したのだ。何を言われたのか、さっぱり理解出来なかった。『お見合い』――なるほど、理解語彙ではある。しかし、シークにとって関わりのある単語だとは全く思ってもみなかった。むしろ、国の主であるゼルダこそ、世継ぎを残すために結婚相手を探さなければならないのではないか。
シークの困惑顔を見てゼルダは、くすっと笑う。今までの緊張はなんだったのか、そのにこにことした顔は明らかにシークの反応を楽しんでいる。珍しく、本当に恨みがましい思いを抱えつつ、そんな表情は表に出せないとばかりに無言でゼルダを見つめると言い訳をするようにクスクスと笑いながら言った。
「だって、あなた、ほんとうに思った通りの反応をするんですもの。そんな目をしても無駄ですわよ」
「……どんな、方なのですか。ボクなんかが相手では、向こうが良い迷惑でしょうに」
「シークの心配は、きっと的外れだと思いますわ。ああ、でも……そうですわね、」
何かを言おうとして、少し顔をしかめる。そのまま、ゼルダは二、三度小さく首を振って「余計なことは言わないことにしますわ」と呟いて、シークにはにっこりと笑顔を向ける。
「とっても良い娘だと伺っています――いえ、とても良い方でしたよ。青い眼が――それも左目のあおさが、本当にうつくしかったのを覚えています」
「あおい、左目……」
「そう。あなたの左目と同じような色。あなたのそれと良く似ているわ。彼女の瞳もあなたのと負けず劣らず、それはそれは美しかったのよ」
「……」
なんとも言えない気持ちが、シークの全身を駆け巡る。
ゼルダは知らない。左目は、彼のコンプレックスなのだと。
彼女は知らないのだ、シークの左目は彼のものではないのだと。
ゼルダに扮するために入れ替えられた青い左目。それと同じうつくしさを持った女性と見合いをすることを思って、シークは気持ちを引き締めた。
そうでないと、その女性に会ったときに、動揺を表に出さない自信がなかったのだ。
「会ってくれますわよね?」
おかげで、ゼルダのこの言葉にも冷静な態度で頷くことが出来た。
ゼルダは嬉しそうにふわりと微笑む。彼女のこの笑顔のためならば、どんなことにでも手を染めることが出来る――たとえそれが、想いを寄せていない女性との婚姻だとしても。シークは改めて、強くそう思った。
(追伸。その左目の使い心地は、如何ですか)
ほんとうにきれいな瞳ね、とゼルダに言われるのが自分の唯一の存在証明といえることだった。
彼女はいつも些細なことまで良く気が付いて、その可憐な唇で褒めてくれる。
自分と、彼女には決して消すことの出来ない身分の差があるのに。
拝啓、左目に不自由したことの無いキミへ。
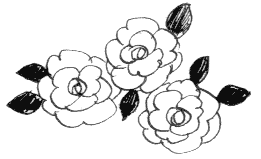
勇者リンクによって魔王ガノンドロフが滅ぼされ、このハイラルに平和がもたらされたのは、もうしばらく前のことになってしまう。連日、復旧作業に追われ、気が付いたらそんなに立っていたのかと暦を見て、シークはふと感傷に浸りそうになっていた。
ハイラルを救った時の勇者のことは、徐々に忘れられていき、今はあの男のことを詳細に覚えているのはごく一部だろう。忘却の呪いにでも掛かったかの様に、民から彼のことが抜けていった。緑の勇者は、魔王と共に滅んでしまった。その証拠に、何処からか現れたあの男は、もう、緑色の衣を纏っていなかった。もはや、勇者ではないのだ。
「おーい、シーク。そういえば、ゼルダが探してたみたいだよ」
出会い頭、軽い調子でリンクは唐突にそう伝えた。それを聞いたシークの反応は素早い。ほぼ完成している城壁に背を預け、昼食を取っていたシークは食事もそのままに立ち上がる。だが、それを苦笑いしながら制したリンクの言い分はこうだった。
「『昼食はきっちり摂ってもらってね』ってゼルダに釘を刺されたんだからな」
ほんっと、融通聞かないなあ、お前は。と言うのは彼に対するリンクの口癖みたいなものだ。シークも真面目な顔を崩さずに「姫がそう仰るのなら」と再び城の陰に座り込んで、手に持っていた食べかけのパンをかじる。
その隣に、自然な動作でリンクは腰掛けて、自分の昼食を取り出した。
リンクはシークやその他大勢の宮廷騎士達とは違い、王家に仕えている訳ではない。彼は誰にも忠誠を誓っていない。ただ、彼の持つ正義――ゼルダを守るという、ただそれだけのためにハイラルの復旧を気まぐれに手伝っていた。彼がやるべきこと、やりたいことは他にあるらしいが、それを口にすることは無い。シークとしても、特に危険視することはないと考えている。というのもリンクの、ゼルダに対するある種の異常な執着は、今のところ彼女を傷つける方向には向かないと判断出来るからだ。シークにとって、王家や国はさして問題ではない。ゼルダが無事ならば、それで構わない。
心の中でそれを再確認をした頃、ちょうど昼食も食べ終わる。シークは零れ落ちたパン屑を払い、無言で立ち上がった。リンクもそれを止める様子は無い。
「ま、がんばれよ」
その表情と口ぶりから、彼はゼルダの話の内容を知っているに違いないと踏んだ。そして、おそらくそれは間違っていないのだろう。
ゼルダはいつも通り、執務室にいた。
いつも通りシークがノックをして名乗ると、すぐに部屋の中から声が聞こえる。どうぞ、と促されて室内へ入る。彼女は既に書類から顔を上げていて、視線がかち合った。
呼びつけたことに軽く謝罪を入れ、シークが呼びつけられることこそが当たり前だと取りなすのは定例と化している。その後、ゼルダは柔らかく微笑んだあと表情を引き締め、シークへ向き直る。
「今回は他でもない、あなたにしか出来ないことを頼みに来たのです」
「……ゼルダが仰るなら」
真面目な表情、そして深刻な声色。ゼルダの言うことならば何でも引き受けると、決意を新たに小さく、しかしはっきりとした声でシークがそう言うと、彼女はコクリと頷いた。
ゼルダはシークが、彼女の頼みを、命令を断らないということを知っているのだ。それが、どういった類いのものだとしても、彼女に忠実であろうとするだろう。それが、彼女には哀しかった。シークが彼女のことを一番に考えるのなら、せめてシークに人並みの幸せになってもらいたい。シークに対するこの任務は、ゼルダのそういった私情と、王宮が求めている利益の両方を兼ね備えたものだった。
沈黙が支配する場。シークはいっさいの感情を外へ出そうとしていなかったが、内心は徐々に緊張してきた。必要とあらば、心を殺してでもなんでもシークへ命令していたゼルダが、ここまで焦らすのは初めてだった。
とうとう彼女は口を開く。うつくしく落ち着いたソプラノの声が、シークの耳へとその指令を運ぶ。
「シーク。二日後のこの時間、お見合いをなさい」
時間が止まった。
正確には、シークの思考が停止したのだ。何を言われたのか、さっぱり理解出来なかった。『お見合い』――なるほど、理解語彙ではある。しかし、シークにとって関わりのある単語だとは全く思ってもみなかった。むしろ、国の主であるゼルダこそ、世継ぎを残すために結婚相手を探さなければならないのではないか。
シークの困惑顔を見てゼルダは、くすっと笑う。今までの緊張はなんだったのか、そのにこにことした顔は明らかにシークの反応を楽しんでいる。珍しく、本当に恨みがましい思いを抱えつつ、そんな表情は表に出せないとばかりに無言でゼルダを見つめると言い訳をするようにクスクスと笑いながら言った。
「だって、あなた、ほんとうに思った通りの反応をするんですもの。そんな目をしても無駄ですわよ」
「……どんな、方なのですか。ボクなんかが相手では、向こうが良い迷惑でしょうに」
「シークの心配は、きっと的外れだと思いますわ。ああ、でも……そうですわね、」
何かを言おうとして、少し顔をしかめる。そのまま、ゼルダは二、三度小さく首を振って「余計なことは言わないことにしますわ」と呟いて、シークにはにっこりと笑顔を向ける。
「とっても良い娘だと伺っています――いえ、とても良い方でしたよ。青い眼が――それも左目のあおさが、本当にうつくしかったのを覚えています」
「あおい、左目……」
「そう。あなたの左目と同じような色。あなたのそれと良く似ているわ。彼女の瞳もあなたのと負けず劣らず、それはそれは美しかったのよ」
「……」
なんとも言えない気持ちが、シークの全身を駆け巡る。
ゼルダは知らない。左目は、彼のコンプレックスなのだと。
彼女は知らないのだ、シークの左目は彼のものではないのだと。
ゼルダに扮するために入れ替えられた青い左目。それと同じうつくしさを持った女性と見合いをすることを思って、シークは気持ちを引き締めた。
そうでないと、その女性に会ったときに、動揺を表に出さない自信がなかったのだ。
「会ってくれますわよね?」
おかげで、ゼルダのこの言葉にも冷静な態度で頷くことが出来た。
ゼルダは嬉しそうにふわりと微笑む。彼女のこの笑顔のためならば、どんなことにでも手を染めることが出来る――たとえそれが、想いを寄せていない女性との婚姻だとしても。シークは改めて、強くそう思った。
宮廷騎士の青年
(追伸。その左目の使い心地は、如何ですか)