My Dear
自分にとってと言うべきか、この一族にとってと言うべきか。
王家という存在、ゼルダという存在は全てだった。
自分の左目を捧げたことに、何一つとして後悔はしていない。
拝啓、左目に不自由したことの無いキミへ。
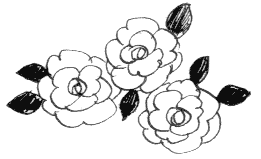
『お見合い』とは言っても、向こうの、そしてシークの希望もあって略式で行なわれることになった。王家が絡むとなれば、もう少し仰々しく執り行われるのが通例ではあるが、ことを大きくしたくないのはお互い様だったらしい。「あの方は、少しおとなしいものですから」とゼルダは少々不満げにそう言うけれど、シークがホッとしたことは確かである。
もう殆ど建て直されているハイラル城の一室を使い、顔合わせが行なわれる。ゼルダの、王家の遠い親戚とも言える身分の女性ではあるらしいのだが、見合い写真を見たところ、シークにはそう似ているとも思えなかった。左側に流された前髪が、彼女の噂の瞳を覆い隠していて、残念だと思った。
彼女とゼルダが似ていなかったのは、彼にとって良いことだったのだろう。ゼルダの影に惑わされずに、相手の女性を見ることが出来る。決して愛している訳ではない、この先も愛すことなどないだろうその女性に、けれど真摯に向き合うことは、出来る。
(そんなことを考えていると、リンクに悟られたりなんかしたら、きっと驚かれるのだろうが)
つまり、シークがゼルダ以外のことを『真摯に向き合おう』としている姿を、他人は知らないということだ。
でも、そういう態度でも無ければ、こういったことは上手く行かないだろうし――それではゼルダも悲しむだろう。何を思ってゼルダがこの件を手配したのか、シークには分かっているつもりだ。幸せにならなければいけない。ゼルダが、シークを幸せにしたいのならば、それをつかみ取るのが、彼の務めであり義務なのだから。
いつものシーカー族としての民族衣装でもなく、『影』として後ろ暗い任務を行なうときの黒いローブでもなく、女王ゼルダ付きの宮廷騎士としての服を着て、シークは廊下を歩いていた。今から会う彼女はきっと、この表の顔でしか、シークのことを知らない。ほとんど名ばかりの身分で、顔をさらすことも殆どしない、こんな偽物の姿で近付くのは公正ではないだろうと思いながらも、シークには今更どうすることもできなかった。
入室すると、相手の方は既に到着していた。どこかぼうっとした様子で、それでも最低限の愛想は失わずに立会人と話しているようだった。噂通りの瞳を覗き込もうとは思いながらも、長く真っ直ぐな茶髪が顔の側面を覆っている。
待たせたことを手短に詫び、立会人の紹介も受けつつ、簡単な自己紹介を済ます。アシナスというらしい彼女のことを写真で見た通りに雰囲気の人だと思いはしたが、あまり不躾に眺めるのも良くないかと思い、眼を伏せつつ立会人が話を進めるのをぼうっと聞いていた。自分のことだというのに、どうにも他人事のように思えてしまう。それに対して、申し訳なさを抱き始めた辺りで、二人きり、部屋に残されることになった。
人と話すこと、それ自体が余り得意ではないのだ――どうしたら良いか内心で慌てていると、相手の女性がおずおずと声を掛けてくる。「あの、」控えめな声だ。戸惑っているのは向こうも同じらしい。それに少しだけ安心しつつ、伏せていた視線を元の位置に戻した。そこで、彼女の左目が真新しい包帯で覆われていることに、ようやく気が付いた。相手に関心がないにもほどがある、自分をそう叱咤しながらもシークは心の中で言い訳をする。そこまで関心を持つように育てられていないのだから、と。
ともかく、ゼルダが褒めていたあの瞳は、今は見ることが出来ないらしい。ほんの少しがっかりした自分がいたことに驚くが、それは表には出さない。無表情をいくらか和らげるように努力して、見合い相手の言葉を待つ。
「あの、きれいな色ですよね」
含みのある声色に聞こえて、シークは少し警戒を強くする。何か、違和感のあるその言い方は、何に対するものなのだろう。シークが無表情のまま首を傾げると、その人は、ふふっと笑って言う。
「あなたの、その左目」
指を指すことはしなかったけれど、眼帯に覆われていない右目は刺すようにシークの顔を見つめている。正確には瞳を凝視しているのだろう、カチリと嵌ったまま視線は動かない。どのくらいそうしていたのか、やがて関心を失ったかのように目を伏せる。
「あなたの瞳も綺麗だと思います……ゼルダと同じような、青い瞳」
「褒め言葉だと思って受け取っておきます。けど、他の女性を引き合いに出すのはあまりお行儀が良くなくてよ」
ふふ、と微笑むその様からは、彼女は気にしていないようでホッとした。たしかに、こういう場でゼルダの名を出すのは良くなかった。本当に対人関係の任務は難しいものだと思って、内心で否定する。これを任務だと思うのは自分の、良くない傾向だ。ゼルダは、きっと単純にしあわせを掴んで欲しいのだから。
ずきり、とどこかが痛む。今までに感じたことのないこの感情の揺れはなんなのだろうか。『しあわせ』という得体の知れないものについて考えると、いつもざわざわと気持ちが波立つ。ハイラル王家だけを見ていたあの時、勇者リンクがハイラルを救うあの瞬間まで、『感情』なんて必要がなかったものだから。
自分の思考の海に溺れそうになっていると、彼女は笑って言う。
「良くも悪くも真面目なのね、あなたって」
「真面目なんかじゃ……真面目なら、最初にきちんと言うだろう。ボクが――ボクがきっとキミを愛せないということを」
言ってしまったと思ったのに、彼女はどうしてかクスクス笑いを始めてしまった。発作のようなそれを止める術をシークは知らない。ただ、困惑したまま見守っていると、彼女はどうにか笑いを止めて微笑んだ。
「わたしの名はアシナスというのです。以後、よろしくお願いします」
「急に何故……先ほども、そう聞いたのに」
「仕切り直しをしましょうってことよ。わたしをきっと愛せないと聞いたあとで。だってそれに、あなた、私の名を呼ばないじゃないの」
「それは……」
「ね、あなたのお名前は?」
にっこりと笑えば、余計にゼルダのようだと思ってしまった。どきり、と心臓が高鳴る。これは、どういう意味の高鳴りなのか、未だ分からない。ただ、ゼルダのような青い瞳と、ゼルダには似ても似つかない顔の造形。彼女を、愛せるだろうか。改めて考えても、答えは否。だけれど、向き合うことは出来るかもしれない。この女性のことは、嫌いじゃない。今はそれで良いのだと言われている気がした。
「ボクはシークだ、アシナス」
思い出したかのように、語尾に彼女の名前をつけて呼べば、アシナスという娘は、何も知らない少女のようにふわりと笑った。「私は、あなたを愛したいわ」そのことばは彼女もまた、自分のことを愛せないと言っているようだと、シークは思う。
* * *
シークが気が付いたときには、手続きは終えられていた。ゼルダが嬉しそうに「あなたが受け入れてくれて本当に良かった」と彼に微笑みかけるまで、シークはあの青い瞳の少女と添い遂げるのだということを現実とは思ってすらいなかったのに。
ゼルダがやけにあの娘に肩入れしていると思い、胸がざわめくが気が付かない振りをしたままシークは言う。
「彼女の――アシナスの左目が見られなかったのが残念だ」
「そうね。彼女の瞳は、ほんとうにきれいだったのに」
ゼルダが少し寂しそうな顔をして、頷いた。「ぜひ、あなたも見るべきだったのよ。彼女の瞳の奥底から輝く、海のような色は、そう見られる物ではありませんもの」
海――書物でしか語られることの無い、塩の含んだ大きな湖。陸の孤島であるハイラルには海がないのだから、想像でしかないけれども。シークの青は、海のようだとは到底言い表せない。
「不思議ですわね。同じような色でも、瞳は心の中を表すのかしら。同じ水でも、底の色や環境が違えば、見える色が違うみたいに」
ゼルダの言葉は、どういった心持ちで発せられたことなのだろう。シークは、真意を問うことが出来なかった。
(ただし、キミのためだったかと思うと口惜しいのは隠せないよ)
<< main >>自分にとってと言うべきか、この一族にとってと言うべきか。
王家という存在、ゼルダという存在は全てだった。
自分の左目を捧げたことに、何一つとして後悔はしていない。
拝啓、左目に不自由したことの無いキミへ。
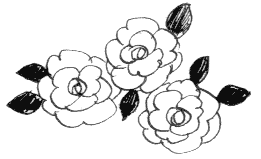
『お見合い』とは言っても、向こうの、そしてシークの希望もあって略式で行なわれることになった。王家が絡むとなれば、もう少し仰々しく執り行われるのが通例ではあるが、ことを大きくしたくないのはお互い様だったらしい。「あの方は、少しおとなしいものですから」とゼルダは少々不満げにそう言うけれど、シークがホッとしたことは確かである。
もう殆ど建て直されているハイラル城の一室を使い、顔合わせが行なわれる。ゼルダの、王家の遠い親戚とも言える身分の女性ではあるらしいのだが、見合い写真を見たところ、シークにはそう似ているとも思えなかった。左側に流された前髪が、彼女の噂の瞳を覆い隠していて、残念だと思った。
彼女とゼルダが似ていなかったのは、彼にとって良いことだったのだろう。ゼルダの影に惑わされずに、相手の女性を見ることが出来る。決して愛している訳ではない、この先も愛すことなどないだろうその女性に、けれど真摯に向き合うことは、出来る。
(そんなことを考えていると、リンクに悟られたりなんかしたら、きっと驚かれるのだろうが)
つまり、シークがゼルダ以外のことを『真摯に向き合おう』としている姿を、他人は知らないということだ。
でも、そういう態度でも無ければ、こういったことは上手く行かないだろうし――それではゼルダも悲しむだろう。何を思ってゼルダがこの件を手配したのか、シークには分かっているつもりだ。幸せにならなければいけない。ゼルダが、シークを幸せにしたいのならば、それをつかみ取るのが、彼の務めであり義務なのだから。
いつものシーカー族としての民族衣装でもなく、『影』として後ろ暗い任務を行なうときの黒いローブでもなく、女王ゼルダ付きの宮廷騎士としての服を着て、シークは廊下を歩いていた。今から会う彼女はきっと、この表の顔でしか、シークのことを知らない。ほとんど名ばかりの身分で、顔をさらすことも殆どしない、こんな偽物の姿で近付くのは公正ではないだろうと思いながらも、シークには今更どうすることもできなかった。
入室すると、相手の方は既に到着していた。どこかぼうっとした様子で、それでも最低限の愛想は失わずに立会人と話しているようだった。噂通りの瞳を覗き込もうとは思いながらも、長く真っ直ぐな茶髪が顔の側面を覆っている。
待たせたことを手短に詫び、立会人の紹介も受けつつ、簡単な自己紹介を済ます。アシナスというらしい彼女のことを写真で見た通りに雰囲気の人だと思いはしたが、あまり不躾に眺めるのも良くないかと思い、眼を伏せつつ立会人が話を進めるのをぼうっと聞いていた。自分のことだというのに、どうにも他人事のように思えてしまう。それに対して、申し訳なさを抱き始めた辺りで、二人きり、部屋に残されることになった。
人と話すこと、それ自体が余り得意ではないのだ――どうしたら良いか内心で慌てていると、相手の女性がおずおずと声を掛けてくる。「あの、」控えめな声だ。戸惑っているのは向こうも同じらしい。それに少しだけ安心しつつ、伏せていた視線を元の位置に戻した。そこで、彼女の左目が真新しい包帯で覆われていることに、ようやく気が付いた。相手に関心がないにもほどがある、自分をそう叱咤しながらもシークは心の中で言い訳をする。そこまで関心を持つように育てられていないのだから、と。
ともかく、ゼルダが褒めていたあの瞳は、今は見ることが出来ないらしい。ほんの少しがっかりした自分がいたことに驚くが、それは表には出さない。無表情をいくらか和らげるように努力して、見合い相手の言葉を待つ。
「あの、きれいな色ですよね」
含みのある声色に聞こえて、シークは少し警戒を強くする。何か、違和感のあるその言い方は、何に対するものなのだろう。シークが無表情のまま首を傾げると、その人は、ふふっと笑って言う。
「あなたの、その左目」
指を指すことはしなかったけれど、眼帯に覆われていない右目は刺すようにシークの顔を見つめている。正確には瞳を凝視しているのだろう、カチリと嵌ったまま視線は動かない。どのくらいそうしていたのか、やがて関心を失ったかのように目を伏せる。
「あなたの瞳も綺麗だと思います……ゼルダと同じような、青い瞳」
「褒め言葉だと思って受け取っておきます。けど、他の女性を引き合いに出すのはあまりお行儀が良くなくてよ」
ふふ、と微笑むその様からは、彼女は気にしていないようでホッとした。たしかに、こういう場でゼルダの名を出すのは良くなかった。本当に対人関係の任務は難しいものだと思って、内心で否定する。これを任務だと思うのは自分の、良くない傾向だ。ゼルダは、きっと単純にしあわせを掴んで欲しいのだから。
ずきり、とどこかが痛む。今までに感じたことのないこの感情の揺れはなんなのだろうか。『しあわせ』という得体の知れないものについて考えると、いつもざわざわと気持ちが波立つ。ハイラル王家だけを見ていたあの時、勇者リンクがハイラルを救うあの瞬間まで、『感情』なんて必要がなかったものだから。
自分の思考の海に溺れそうになっていると、彼女は笑って言う。
「良くも悪くも真面目なのね、あなたって」
「真面目なんかじゃ……真面目なら、最初にきちんと言うだろう。ボクが――ボクがきっとキミを愛せないということを」
言ってしまったと思ったのに、彼女はどうしてかクスクス笑いを始めてしまった。発作のようなそれを止める術をシークは知らない。ただ、困惑したまま見守っていると、彼女はどうにか笑いを止めて微笑んだ。
「わたしの名はアシナスというのです。以後、よろしくお願いします」
「急に何故……先ほども、そう聞いたのに」
「仕切り直しをしましょうってことよ。わたしをきっと愛せないと聞いたあとで。だってそれに、あなた、私の名を呼ばないじゃないの」
「それは……」
「ね、あなたのお名前は?」
にっこりと笑えば、余計にゼルダのようだと思ってしまった。どきり、と心臓が高鳴る。これは、どういう意味の高鳴りなのか、未だ分からない。ただ、ゼルダのような青い瞳と、ゼルダには似ても似つかない顔の造形。彼女を、愛せるだろうか。改めて考えても、答えは否。だけれど、向き合うことは出来るかもしれない。この女性のことは、嫌いじゃない。今はそれで良いのだと言われている気がした。
「ボクはシークだ、アシナス」
思い出したかのように、語尾に彼女の名前をつけて呼べば、アシナスという娘は、何も知らない少女のようにふわりと笑った。「私は、あなたを愛したいわ」そのことばは彼女もまた、自分のことを愛せないと言っているようだと、シークは思う。
シークが気が付いたときには、手続きは終えられていた。ゼルダが嬉しそうに「あなたが受け入れてくれて本当に良かった」と彼に微笑みかけるまで、シークはあの青い瞳の少女と添い遂げるのだということを現実とは思ってすらいなかったのに。
ゼルダがやけにあの娘に肩入れしていると思い、胸がざわめくが気が付かない振りをしたままシークは言う。
「彼女の――アシナスの左目が見られなかったのが残念だ」
「そうね。彼女の瞳は、ほんとうにきれいだったのに」
ゼルダが少し寂しそうな顔をして、頷いた。「ぜひ、あなたも見るべきだったのよ。彼女の瞳の奥底から輝く、海のような色は、そう見られる物ではありませんもの」
海――書物でしか語られることの無い、塩の含んだ大きな湖。陸の孤島であるハイラルには海がないのだから、想像でしかないけれども。シークの青は、海のようだとは到底言い表せない。
「不思議ですわね。同じような色でも、瞳は心の中を表すのかしら。同じ水でも、底の色や環境が違えば、見える色が違うみたいに」
ゼルダの言葉は、どういった心持ちで発せられたことなのだろう。シークは、真意を問うことが出来なかった。
青い眼の君
(ただし、キミのためだったかと思うと口惜しいのは隠せないよ)