From
敬具、左目が無くてもしあわせなわたし。
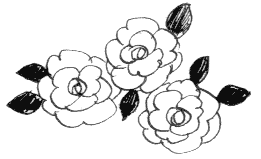
――最後に記し筆を置いた彼女は、文机の傍らにある書き貯めた紙の束を手に取って過去を思い返すように微笑んだ。日記代わりに毎日一枚ずつ、貴重な紙を消費して書いていたそれらは、届けられることのなかった手紙だった。
(捨ててしまおうか)
名残惜しくはあったが、過去の自分――ただひたすらに左目を奪った存在を恨んでいたあの頃の自分と決別するにはちょうど良い。そう思って、かまどへ向かう為に立ち上がろうとしたその時、背後から手が伸びてきた。
「なんだい、これは」
「わ、シーク!」
驚いて叫び声を上げてしまったのも、無理がない。今では伴侶となったこの男は、癖なのか知らないけれど、共に暮らし始めてからもずっと気配を消しているし、今も例外ではなかった。その上、この紙の束は彼に向けられた呪詛の山。一番見られたくない相手に、自分の後ろ暗い過去を一枚抜き取られ、アシナスは焦って声を上げる。
それを気にする様子もなく、シークは結われた三つ編みを揺らしながら頭を傾け、さっと本文へ目を通す。「差し詰め、僕への恋文ってところだね」ゆっくりと、アシナスの過去を許すように目を細めて囁いたその言葉に、深くにもアシナスは照れた。彼のことばはいつもそうだ。どことなく甘さを孕んだ、苦みの塊である。だって、どうしてこの人は。彼女の過ちや行いは許容するのに、反面自分の落ち度はいつまで経っても許せやしない。今だって、彼女の左目を無自覚に使用していた自分の過去を憤りながらも、守るべき唯一絶対の主のためには仕方がなかったのだと矛盾する気持ちを押さえつけていたのだろう。
けれど、そういった歪(ひず)みまでが、アシナスは愛おしくて仕方がない。だが、そのことをあの時みたいに、いちいち紙に記そうとは思わない。呪詛も手も届かない遠い存在だったあの頃と違って、四六時中、頭の中からはなれない存在は今、目の前にいる。不定期の任務でそりゃあ、常に共にいることは敵わないけれど、それでも今の彼の居場所は彼女の隣だ。優先順位は前と変わらず、ゼルダ姫の次だったとしても、今のアシナスにはシークの隣に立つ権利があるのだから。
「もうこんなことは書かないわよ。いつまでも持っていたって仕方がないから、燃やそうと思ったの」
「君が燃やしたいならそうすれば良い。ただ……」
「ただ?」
「……折角、君が、昔から僕のことだけを考えてくれていた証なのに、と思っただけだ。気にしないで」
(だから、どうして、この人はこう……)
シークのこういった言い回しが、アシナスは苦手だった。彼が本気でそう思っていると分かっている以上、余計にどういう反応をしていいのかが分からないのだ。昔とは違い、自分の存在を意識しているのだと、そうさせたのはアシナスだと、言葉を変え、場面を変え、繰り返し繰り返し伝えられる度に彼女の心臓は刻まれる。あの時、自分が抱いていた羨望や、憎しみや、恨み言の全てが彼に向かっていて、時を経てそれを受け止めてもらえているんだと知れば、あの頃の自分はなんと思うのだろうか。
(やっぱり、捨ててしまおう)
後悔するのだと分かっていて、アシナスは立ち上がろうとする。その行動を分かっていたのか、シークは制するように後ろからそっと抱きしめた。自分なんかよりも随分と小さな身体。ゼルダ姫よりももっと小柄に見える彼女をすっぽりと腕の中に抱きしめて、シークは彼女の耳元に顔を寄せる。さらりと、金の髪の毛が揺れて、長い前髪が彼女の耳へと触れた。何度、接触しても慣れることがない。後ろから包み込まれる度に、胸の内側から叩き付けられる鼓動を息を薄くすることで押さえ込もうとするが上手く行かない。アシナスは震える指先を誤摩化すように、顔の隣へと垂れてきていた彼の三つ編みをそっと握って、結び目を解く。うねりつつも解放された髪の毛は散らばって、理性と結界が崩壊しつつあることを主張していた。
シークがそっと彼女の耳を甘噛み、小さく「捨てないで」の一言。言葉と同時に掛かる吐息が唾液で濡れた肌へ触れて、ひんやりと冷える。熱さと冷たさを同時に加えられるような感覚がこそばゆいが、全身は熱を持つばかり。
(彼は、三つ編みが解けると、自分に素直になるのだ)
これは最近の発見だった。捨てないで欲しいと思っていたことは分かっていたのに、捨てようとした。そんな自分に対して、気持ちを主張してくれたのがどうしようもなく嬉しい。捨てようしたその動作を事前に分かってくれたのも、嬉しい。何よりも、お互いがお互いの気持ちをほんの少しとはいえ、理解出来る程に近付いていると実感することが、アシナスにはこの上ない喜びだった。
気持ちを預けるように、彼女はシークの胸に体重を預ける。彼もそれを受け止めてそっと抱きしめる手を強くした。
「ねえ、シーク」
アシナスが名前を唇に乗せると、シークは彼女のつけている眼帯を外し、窪んだ左目の瞼をそっと撫でた。後ろから抱きしめているだけでは足りないというかのように、性急に彼女に回していた腕を解き、向かい合わせになる。触れ合っていたところに空いた隙間、空気が入り込んできて少し肌寒い。だがその物足りなさも見つめ合うことで生まれた熱によって打ち消される。爛々と青めく、失われてはいない右目。そして、彼の赤い瞳がかち合った。「アシナス」名前を呼び、それが合図であったかのように顔を寄せる。シークは贖罪するかのように、そっとアシナスの左目に接吻を施し、そしてそのまま唇を彼女のそこへ重ねた。
(おしまい)
<< main 敬具、左目が無くてもしあわせなわたし。
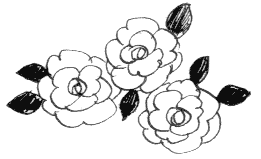
――最後に記し筆を置いた彼女は、文机の傍らにある書き貯めた紙の束を手に取って過去を思い返すように微笑んだ。日記代わりに毎日一枚ずつ、貴重な紙を消費して書いていたそれらは、届けられることのなかった手紙だった。
(捨ててしまおうか)
名残惜しくはあったが、過去の自分――ただひたすらに左目を奪った存在を恨んでいたあの頃の自分と決別するにはちょうど良い。そう思って、かまどへ向かう為に立ち上がろうとしたその時、背後から手が伸びてきた。
「なんだい、これは」
「わ、シーク!」
驚いて叫び声を上げてしまったのも、無理がない。今では伴侶となったこの男は、癖なのか知らないけれど、共に暮らし始めてからもずっと気配を消しているし、今も例外ではなかった。その上、この紙の束は彼に向けられた呪詛の山。一番見られたくない相手に、自分の後ろ暗い過去を一枚抜き取られ、アシナスは焦って声を上げる。
それを気にする様子もなく、シークは結われた三つ編みを揺らしながら頭を傾け、さっと本文へ目を通す。「差し詰め、僕への恋文ってところだね」ゆっくりと、アシナスの過去を許すように目を細めて囁いたその言葉に、深くにもアシナスは照れた。彼のことばはいつもそうだ。どことなく甘さを孕んだ、苦みの塊である。だって、どうしてこの人は。彼女の過ちや行いは許容するのに、反面自分の落ち度はいつまで経っても許せやしない。今だって、彼女の左目を無自覚に使用していた自分の過去を憤りながらも、守るべき唯一絶対の主のためには仕方がなかったのだと矛盾する気持ちを押さえつけていたのだろう。
けれど、そういった歪(ひず)みまでが、アシナスは愛おしくて仕方がない。だが、そのことをあの時みたいに、いちいち紙に記そうとは思わない。呪詛も手も届かない遠い存在だったあの頃と違って、四六時中、頭の中からはなれない存在は今、目の前にいる。不定期の任務でそりゃあ、常に共にいることは敵わないけれど、それでも今の彼の居場所は彼女の隣だ。優先順位は前と変わらず、ゼルダ姫の次だったとしても、今のアシナスにはシークの隣に立つ権利があるのだから。
「もうこんなことは書かないわよ。いつまでも持っていたって仕方がないから、燃やそうと思ったの」
「君が燃やしたいならそうすれば良い。ただ……」
「ただ?」
「……折角、君が、昔から僕のことだけを考えてくれていた証なのに、と思っただけだ。気にしないで」
(だから、どうして、この人はこう……)
シークのこういった言い回しが、アシナスは苦手だった。彼が本気でそう思っていると分かっている以上、余計にどういう反応をしていいのかが分からないのだ。昔とは違い、自分の存在を意識しているのだと、そうさせたのはアシナスだと、言葉を変え、場面を変え、繰り返し繰り返し伝えられる度に彼女の心臓は刻まれる。あの時、自分が抱いていた羨望や、憎しみや、恨み言の全てが彼に向かっていて、時を経てそれを受け止めてもらえているんだと知れば、あの頃の自分はなんと思うのだろうか。
(やっぱり、捨ててしまおう)
後悔するのだと分かっていて、アシナスは立ち上がろうとする。その行動を分かっていたのか、シークは制するように後ろからそっと抱きしめた。自分なんかよりも随分と小さな身体。ゼルダ姫よりももっと小柄に見える彼女をすっぽりと腕の中に抱きしめて、シークは彼女の耳元に顔を寄せる。さらりと、金の髪の毛が揺れて、長い前髪が彼女の耳へと触れた。何度、接触しても慣れることがない。後ろから包み込まれる度に、胸の内側から叩き付けられる鼓動を息を薄くすることで押さえ込もうとするが上手く行かない。アシナスは震える指先を誤摩化すように、顔の隣へと垂れてきていた彼の三つ編みをそっと握って、結び目を解く。うねりつつも解放された髪の毛は散らばって、理性と結界が崩壊しつつあることを主張していた。
シークがそっと彼女の耳を甘噛み、小さく「捨てないで」の一言。言葉と同時に掛かる吐息が唾液で濡れた肌へ触れて、ひんやりと冷える。熱さと冷たさを同時に加えられるような感覚がこそばゆいが、全身は熱を持つばかり。
(彼は、三つ編みが解けると、自分に素直になるのだ)
これは最近の発見だった。捨てないで欲しいと思っていたことは分かっていたのに、捨てようとした。そんな自分に対して、気持ちを主張してくれたのがどうしようもなく嬉しい。捨てようしたその動作を事前に分かってくれたのも、嬉しい。何よりも、お互いがお互いの気持ちをほんの少しとはいえ、理解出来る程に近付いていると実感することが、アシナスにはこの上ない喜びだった。
気持ちを預けるように、彼女はシークの胸に体重を預ける。彼もそれを受け止めてそっと抱きしめる手を強くした。
「ねえ、シーク」
アシナスが名前を唇に乗せると、シークは彼女のつけている眼帯を外し、窪んだ左目の瞼をそっと撫でた。後ろから抱きしめているだけでは足りないというかのように、性急に彼女に回していた腕を解き、向かい合わせになる。触れ合っていたところに空いた隙間、空気が入り込んできて少し肌寒い。だがその物足りなさも見つめ合うことで生まれた熱によって打ち消される。爛々と青めく、失われてはいない右目。そして、彼の赤い瞳がかち合った。「アシナス」名前を呼び、それが合図であったかのように顔を寄せる。シークは贖罪するかのように、そっとアシナスの左目に接吻を施し、そしてそのまま唇を彼女のそこへ重ねた。
左目の少女
(おしまい)