My Dear
美しい瞳を持つ人間が、本当は心底羨ましかった
彼女から褒められるこの瞳がまがい物であることが、許しがたかった。
だから、キミのことは、絶対に愛せないと思っていたのに。
拝啓、左目に不自由したことの無いキミへ。
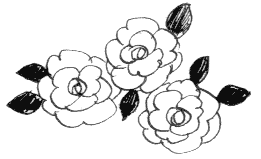
アシナスは、その眼球をどうすればいいのか、本能で分かっていたようだった。誰に指示されるでも無く、彼女はそれを両手で包む。握りつぶしてしまうのではないかというほど、しかし破裂はしないぎりぎりの程度に力を込めると、言わなければならないという強迫観念に駆られて、脳裏に浮かんだ言葉を囁く。ハイリア古語と言っても良いだろう、今では使われていないその言葉を紡ぎ終わった時、その左目だった眼球が弾けとんだ。周囲に青い光が充満する。無事であるはずの右目すらも作用を止めてしまう程の明るさに慣れるまでが十数秒。しかし、その間に、絶叫が二重になったことに、彼女は気が付いた。
元々は自分の物ではないとはいえ、左目をえぐり出されたシークの悲鳴に重ねるようにして、あの口の悪い『影』が叫んでいた。リンクに似た声質だったそれが、魔物の甲高い喚き声に変わり、そして光の収束とともに静まっていく。
漸(ようや)く周囲が見渡せるようになった時には、『影』の闇色は薄くなっており、もう殆ど鼠色だった。
「今度は、俺の出番が無かったな」
リンクが少し寂しそうだったのは気のせいだろうか。黒く濁った水が聖剣マスターソードにまとわりついているのを、何度か剣を振ることによって払った彼は、私を一瞥すると未だ転げ回っているシークの元へ寄った。
シークの叫び声はそろそろ収まっていた。喉もやられてしまったのだろう、咽頭に掠れて漏れ聞こえるような息づかいを激しく繰り返し、時折ぶるぶるっと震えていた。大きく上下に揺れる肩。両手で押さえられる左目。元々彼の物ではないとはいえ、魔法での補助も無しに眼球を抉り取られたのだから、痛みと恐怖は想像しがたいものがあるのだろう。
アシナスもリンクに続いて、上手く動かない身体を動かして決死の思いで彼の元へと、這いずりながら向かう。幸い距離もそれほど離れていなかったので、魔物に振り回されて衰弱した身体でも辿り着くことが出来た。
「魔力のある眼球が、お前の元から離れたのだから、痛みもひとしおだろうな」
「……リン、ク」
痛みによる汗が水浸しの床に流れているシークの様子は、なんと表現して良いかアシナスには分かりかねた。ただ、何かを伝えようと息も絶え絶えに声を上げたシークを見ていると、今までに抱いたことの無い感情が込み上げてきた。
どうしようもなく、憎い人だったのに。
一生かかったところで、許すことは出来ないと思っていた。
彼の望んだことじゃないこととは分かっていても、先祖から受け継いだ魔力を孕んだ眼球を持っていかれたことに、どうして恨まずにいられるだろう。あれが、あれこそが私の唯一の長所と言っても良かったのにと、彼女は常々思っていた。左目が空っぽ、傷物になってしまったアシナスは、この先ゆっくりと何事も無く朽ち果てるのだろうと思っていた。行き遅れ《オールド・ミス》になる覚悟なんて、疾うにしていた。
だけど、何の因果だかこの男と見合いをすることになって、憎いところだけの人間ではないと知って見直し始めていたところに、魔物に襲われたのだ。彼は、シークは私を切り捨てた。見合いの席で無言の宣言をしたように、女王を選んだ。皮肉な話だが、アシナスはそこに心を惹かれてしまったのだ。
そこには、表向きの宮廷騎士の肩書きも、影武者としての役割も、女王に付き従うものとしての使命も、シーカー族としての生い立ちも、何もかもが関係なかった。シークは、ゼルダを選べるのだと思った。何も選んでこなかった自分とは、まるで違うと彼女は心の中で自嘲する。
(あわよくば、私をも選んで欲しいと――そんな浅ましいことを)
ゼルダの代わりとか、ゼルダの次で良いとか、そんなことは言わない。ただ、数ある選択肢の中から自分を選んで欲しいと、そう思ったのだ。
それを見透かしたかのように、芋虫のように横たわるシークは左目を抑えたまま右目を少しだけ細めてふわりと笑った。左目に埋め込まれたアシナスの眼球の魔力で同じ青色に染まっていたのだろう、彼のその右目は、既に赤色になっている。初めて見るにも関わらず、その色はとてもシークに似合っていると彼女は思った。眼の色ももはや違う、なのにその微笑みは何処かゼルダに似ていて――リンクもそう思ったのか、ハッと息を呑むのが聞こえてきた。
「シーク。お前、」
「リン、ク……アシナスを、頼んだ」
今持てる最後の力を振り絞ってそう言ってるだろうシークに、リンクは行儀の悪い舌打ちをした。似合わないと、アシナスは素直に思いながら、膝をついてシークの様子を見ているリンクを見る。彼が何かを言おうとしたが、シークはまたそれを遮った。
「それ、から……早く、とどめを」
「ばっ、気付いていたのなら、それを先に言え!!」
シークが傷の無い右目で示した視線の先には、先ほど絶叫とともに倒れ込んだ『影』がいた。もぞもぞと動いている姿は気味が悪い。溶けて消えてしまうかと思った彼は、徐々に形を再生していく。最初は大まかな形、そして細部に至るまでゆっくりと再現。まるで目の前にいるリンクを模写していくような様子にゾッとする。
リンクはもう一度、舌打ちをした。『影』のそれとも重なって、本当は見た目よりもずっとずっと狭いのだろう空間に響き渡る。
「おとなしく死んどけよ、ダーク」
「るせえ、猪口才(ちょこざい)な真似しやがって」
お互い剣を振りかぶりながらも会話が出来るなんて、まあ、余裕なことだとアシナスは状況を忘れて感心してしまうところだった。
「魔王がいなくてはお前の存在意義なんてないだろうに――何をそんなに頑張ってんだよ」
吐き捨てるように言った、リンクの言葉はこの場にいる全員を傷つけて彼自身の元へ戻っていった。ピクリと身体を震わせ息を止めたシークの様子を尻目に、『影』の動きが鈍くなる、その隙を見逃さずにリンクはまがい物の聖剣を弾いた。
リンクは油断なく『影』を追いつめ、その首筋にマスターソードを突きつけつつ問いかけた。
「その、眼の魔力さえあれば、俺は――俺らは自由になれたんだ」
「あのファントムガノンも目的を同じくしたってわけか」
「元々は奴の提案さ。その娘の屋敷に、奴の憑依する絵が飾ってあったろ。そこから得た情報なんだ。なのに、だ。笑っちまうね。俺より先に、てめぇに斬り裂かれたってんだからよ」
『影』はそこまで言うと、もう他に語ることはないとでも言うかのように口を一度閉じた。その場には沈黙が流れる。数秒後、口を開いたのはまたしても『影』だった。
「気が利かねぇ奴だな、てめぇは。とっとと、殺せよ。現世で自由になれないというのなら、とっとと消せ」
「……」
「躊躇うな。お前は、勇者だろ。俺の、持ち主だろう?」
ニッ、と口元だけ歪めての笑みだった。それは『影』の今までの物と似ていたけれど、どこか邪気が薄れたようにアシナスは感じた。
リンクは『勇者』の言葉に、一瞬だけ何かを耐えるように奥歯を噛み締めていたが、その後に弱々しく笑んだ。
「そうだな。俺がやるべきだ。おとなしく、俺の元に還れ。ダークリンク」
強い力は篭っていなさそうだった。最低限の力で『影』を斬った。まっぷたつに切り裂かれた影は、黒が薄れていきそして、水になって消えた。
気が付いたら、そこは何の変哲も無いただの部屋だった。石畳を敷き詰められた飾り気も無い殺風景な部屋。リンクが周囲を見回して、ほっとため息をつく。私もつられて安堵の息を漏らした。
「これでいいだろ、シーク」
「ああ、あとはアシナスを……」
「ばっか、お前もだよ」
リンクの声は柔らかかった。マスターソードを鞘にしまい、先にアシナスを右手で乱暴に抱えたかと思うと、反対の肩にシークを抱え込む。「ボクはもう……」「むしろ死んだ方が」そんなことをぶつぶつと呟いている彼に「シーク」アシナスは思わず呼びかけていた。気を張った、冷たい声色だと彼女は自分で思った。
「ここで死んで逃げるなんて許さない」
「何故だ……キミはボクを恨んでいたはずじゃ」
「許さない」
それはアシナスの本音だった。
死んで楽になろうなんて、許さない。死んでひとりだけ解放されようだなんて許さない。なにより――
(死んで、私から逃げようなんて許さない)
ようやく、過去の恨みも何も無く、この男に向き直れると思ったのに。こんなところでひとり逃げるなんて。
「私を傷物にした、責任を取ってもらわなきゃ困るでしょう?」
オールド・ミスだなんてまっぴらごめんだわ、なんて言うとシークは納得したようなしていないような声色で「わかった」とだけ従順に言う。シークの声に、今まで気を張っていたアシナスの全身から力が抜ける。眼球を握っていた手も緩み、ころりと零れ落ちる。
彼女の状態の変化に、話が一区切りついたのだと判断したリンクは聞き分けの無い子どもに言い聞かせるようにシークに声を掛けた。
「わかったら、シーク。旋律だ。城に帰るぞ」
両手を塞がっているリンクの状況に気が付いて、シークは頷いて何処からとも無くハープを取り出す。どこかで聞いたことがあるような厳かな音が狭い部屋に響いた。旋律が終わると同時に、三人の姿は消えていた。
その場には、ただ色の無くなった眼球のみが転がっている。
* * *
* * *
「温泉?」
城から二人の暮らす屋敷に返ってきたシークの言葉に、アシナスは思わずそう聞き返していた。左目は、眼球を王家に捧げた時から変わらず眼帯をつけているが、弄られていない右目はその青い目を大きく見開いている。だって、温泉だなんて聞きなれない言葉。それもそうだ。今までこの国にはそんなものはなかったのだから。
シークが表舞台に立って久しい――そんな彼の妻となった彼女も外交に関わってきていたのだから、外の国にはそのようなものがあることは彼女も知っていたけれど、『温泉にいかないか』だなんて言葉をこの国で、それもシークから聞くとは思いにもよらなかった。
「少し遅れたハネムーンってこと?」
ハネムーンとは、外の国の結婚に関する習慣らしい。外からの文化に触れたこの王国の民が、えらくそれを気に入ったらしく、小さなムーブメントを起こしていた――元々、蜜月を意味していたらしいこの言葉は、この国では婚姻した男女の親交を深める旅行へと意味を狭めていた。むしろ、この国の伝統では婚姻からしばらくは家から出ないことを推奨されていたのに、なんだかおかしい。
だけど、シークはいつかよりもずいぶんと柔らかくなった表情筋をふ、と緩ませながらも首を横に振った。
「違うよ。それもありだけど――それよりも、結婚の儀式の時に身体を清めなかっただろう?」
「ええ、まあ」
「それに、あんなことがあった後も結局は祈祷による払いで済ませてしまった」
あんなこと――結婚の儀式で花嫁が魔物にさらわれるという前代未聞のあの事件のことを、シークがこうやって触れるのは初めてだった。季節はあれから一回りしている。傷を癒すのにそれだけかかったのか。それとも、アシナスとシークが気を使わなくて済むほどに距離が縮まったのだろうか。後者だと嬉しい。アシナスはそう思いながらも「別にかまわないじゃないの」と素っ気ない返事をしてしまう。
「だって、あれからなにも起きてないでしょう」
「これから起きるかもしれない。それに実は、公務の一環でもあるんだ」
「どういうこと?」
「デスマウンテンの頂上、昔、大妖精の泉があったところに、温泉が沸いたそうだ」
ゴロン族はそれを売りにして観光客を呼びたいらしい。そのための協力を頼まれたんだとシークは少し気まずそうに言う。
先にそう言えばいいのに。アシナスは思ったけれどすぐに考え直す。
(でも、きっと、シークが私と一緒にいきたいと――私を気遣ってくれたのは本当なのよ)
ふふ、と思わず笑みをこぼす。
その意味をたぶん、シークは理解出来ない。それでいいのだ。それでも、彼女と彼が見合いをしたそのときよりも、近付いているのはたしかなのだから。
「そうね。行きましょう。私、ぜひ行きたい」
アシナスの屈託の無いその言葉に、シークは安心したように微笑む。これも、シークが今まで見せることの無かったものだ。シークはゼルダ以外のひとと関わることで、きっと人間になったのだ。彼を支えていた、彼に人間離れした魔力を与えていたアシナスの青い瞳はもう彼の元にはない。それでも、彼はきっと、ゼルダのことを何よりも優先するだろうけれど。
それでも、シークはアシナスを選んだのだと彼女は知っている。罪悪感からか、同上からか、それとも何か別の感情か――彼女には明確には分からないけれど、死んでしまうよりも、彼女と生きることを選んだのは間違いない。
「シーク、私、もうあなたを愛したいだなんて、絶対に言わない」
唐突なアシナスの言葉に、シークは儚くも柔らかい微笑みを浮かべたまま頷いた。歌うような声が、窓から入ってきた風に乗る。
「ボクも、キミを愛せないだなんて二度と言わない」
愛せるかどうかなんて、まだ分からない。今抱いているこの感情は愛に限りなく近い何かな気がする。だけれど、それでもまだ、この蕾みは愛になりきっていないのだ。
(そうね。『恋』から始めてみるも悪くはないわ――)
一般的に言われている、恋とも少し違うのかもしれない。だけれど、彼を見る度に心臓が変な方向に跳ねて、いろんなことを考えてしまうのは間違いない。彼に憎しみを抱いていたあの頃と同じくらい、シークのことを考えてしまう。だけど、後味がまるで違うのだ。口にすると、蜜のように甘く、毒のように繰り返し欲しくなってしまう。
「なんてことをしてくれたのよ」
結局、シークという男から、アシナスは離れられないのだ。彼を恨んでいたあの頃と、もっと違う感情が芽生えている今は同じ。結局、自分が自分ではないようなこの気持ちを味合わされるのだ。きょとんとした表情を浮かべているシークには悪いが、恨み言は、まだまだ収まりそうには無い。
The END.
(⇒おまけのその後)
<< main 美しい瞳を持つ人間が、本当は心底羨ましかった
彼女から褒められるこの瞳がまがい物であることが、許しがたかった。
だから、キミのことは、絶対に愛せないと思っていたのに。
拝啓、左目に不自由したことの無いキミへ。
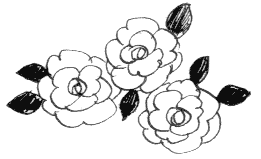
アシナスは、その眼球をどうすればいいのか、本能で分かっていたようだった。誰に指示されるでも無く、彼女はそれを両手で包む。握りつぶしてしまうのではないかというほど、しかし破裂はしないぎりぎりの程度に力を込めると、言わなければならないという強迫観念に駆られて、脳裏に浮かんだ言葉を囁く。ハイリア古語と言っても良いだろう、今では使われていないその言葉を紡ぎ終わった時、その左目だった眼球が弾けとんだ。周囲に青い光が充満する。無事であるはずの右目すらも作用を止めてしまう程の明るさに慣れるまでが十数秒。しかし、その間に、絶叫が二重になったことに、彼女は気が付いた。
元々は自分の物ではないとはいえ、左目をえぐり出されたシークの悲鳴に重ねるようにして、あの口の悪い『影』が叫んでいた。リンクに似た声質だったそれが、魔物の甲高い喚き声に変わり、そして光の収束とともに静まっていく。
漸(ようや)く周囲が見渡せるようになった時には、『影』の闇色は薄くなっており、もう殆ど鼠色だった。
「今度は、俺の出番が無かったな」
リンクが少し寂しそうだったのは気のせいだろうか。黒く濁った水が聖剣マスターソードにまとわりついているのを、何度か剣を振ることによって払った彼は、私を一瞥すると未だ転げ回っているシークの元へ寄った。
シークの叫び声はそろそろ収まっていた。喉もやられてしまったのだろう、咽頭に掠れて漏れ聞こえるような息づかいを激しく繰り返し、時折ぶるぶるっと震えていた。大きく上下に揺れる肩。両手で押さえられる左目。元々彼の物ではないとはいえ、魔法での補助も無しに眼球を抉り取られたのだから、痛みと恐怖は想像しがたいものがあるのだろう。
アシナスもリンクに続いて、上手く動かない身体を動かして決死の思いで彼の元へと、這いずりながら向かう。幸い距離もそれほど離れていなかったので、魔物に振り回されて衰弱した身体でも辿り着くことが出来た。
「魔力のある眼球が、お前の元から離れたのだから、痛みもひとしおだろうな」
「……リン、ク」
痛みによる汗が水浸しの床に流れているシークの様子は、なんと表現して良いかアシナスには分かりかねた。ただ、何かを伝えようと息も絶え絶えに声を上げたシークを見ていると、今までに抱いたことの無い感情が込み上げてきた。
どうしようもなく、憎い人だったのに。
一生かかったところで、許すことは出来ないと思っていた。
彼の望んだことじゃないこととは分かっていても、先祖から受け継いだ魔力を孕んだ眼球を持っていかれたことに、どうして恨まずにいられるだろう。あれが、あれこそが私の唯一の長所と言っても良かったのにと、彼女は常々思っていた。左目が空っぽ、傷物になってしまったアシナスは、この先ゆっくりと何事も無く朽ち果てるのだろうと思っていた。行き遅れ《オールド・ミス》になる覚悟なんて、疾うにしていた。
だけど、何の因果だかこの男と見合いをすることになって、憎いところだけの人間ではないと知って見直し始めていたところに、魔物に襲われたのだ。彼は、シークは私を切り捨てた。見合いの席で無言の宣言をしたように、女王を選んだ。皮肉な話だが、アシナスはそこに心を惹かれてしまったのだ。
そこには、表向きの宮廷騎士の肩書きも、影武者としての役割も、女王に付き従うものとしての使命も、シーカー族としての生い立ちも、何もかもが関係なかった。シークは、ゼルダを選べるのだと思った。何も選んでこなかった自分とは、まるで違うと彼女は心の中で自嘲する。
(あわよくば、私をも選んで欲しいと――そんな浅ましいことを)
ゼルダの代わりとか、ゼルダの次で良いとか、そんなことは言わない。ただ、数ある選択肢の中から自分を選んで欲しいと、そう思ったのだ。
それを見透かしたかのように、芋虫のように横たわるシークは左目を抑えたまま右目を少しだけ細めてふわりと笑った。左目に埋め込まれたアシナスの眼球の魔力で同じ青色に染まっていたのだろう、彼のその右目は、既に赤色になっている。初めて見るにも関わらず、その色はとてもシークに似合っていると彼女は思った。眼の色ももはや違う、なのにその微笑みは何処かゼルダに似ていて――リンクもそう思ったのか、ハッと息を呑むのが聞こえてきた。
「シーク。お前、」
「リン、ク……アシナスを、頼んだ」
今持てる最後の力を振り絞ってそう言ってるだろうシークに、リンクは行儀の悪い舌打ちをした。似合わないと、アシナスは素直に思いながら、膝をついてシークの様子を見ているリンクを見る。彼が何かを言おうとしたが、シークはまたそれを遮った。
「それ、から……早く、とどめを」
「ばっ、気付いていたのなら、それを先に言え!!」
シークが傷の無い右目で示した視線の先には、先ほど絶叫とともに倒れ込んだ『影』がいた。もぞもぞと動いている姿は気味が悪い。溶けて消えてしまうかと思った彼は、徐々に形を再生していく。最初は大まかな形、そして細部に至るまでゆっくりと再現。まるで目の前にいるリンクを模写していくような様子にゾッとする。
リンクはもう一度、舌打ちをした。『影』のそれとも重なって、本当は見た目よりもずっとずっと狭いのだろう空間に響き渡る。
「おとなしく死んどけよ、ダーク」
「るせえ、猪口才(ちょこざい)な真似しやがって」
お互い剣を振りかぶりながらも会話が出来るなんて、まあ、余裕なことだとアシナスは状況を忘れて感心してしまうところだった。
「魔王がいなくてはお前の存在意義なんてないだろうに――何をそんなに頑張ってんだよ」
吐き捨てるように言った、リンクの言葉はこの場にいる全員を傷つけて彼自身の元へ戻っていった。ピクリと身体を震わせ息を止めたシークの様子を尻目に、『影』の動きが鈍くなる、その隙を見逃さずにリンクはまがい物の聖剣を弾いた。
リンクは油断なく『影』を追いつめ、その首筋にマスターソードを突きつけつつ問いかけた。
「その、眼の魔力さえあれば、俺は――俺らは自由になれたんだ」
「あのファントムガノンも目的を同じくしたってわけか」
「元々は奴の提案さ。その娘の屋敷に、奴の憑依する絵が飾ってあったろ。そこから得た情報なんだ。なのに、だ。笑っちまうね。俺より先に、てめぇに斬り裂かれたってんだからよ」
『影』はそこまで言うと、もう他に語ることはないとでも言うかのように口を一度閉じた。その場には沈黙が流れる。数秒後、口を開いたのはまたしても『影』だった。
「気が利かねぇ奴だな、てめぇは。とっとと、殺せよ。現世で自由になれないというのなら、とっとと消せ」
「……」
「躊躇うな。お前は、勇者だろ。俺の、持ち主だろう?」
ニッ、と口元だけ歪めての笑みだった。それは『影』の今までの物と似ていたけれど、どこか邪気が薄れたようにアシナスは感じた。
リンクは『勇者』の言葉に、一瞬だけ何かを耐えるように奥歯を噛み締めていたが、その後に弱々しく笑んだ。
「そうだな。俺がやるべきだ。おとなしく、俺の元に還れ。ダークリンク」
強い力は篭っていなさそうだった。最低限の力で『影』を斬った。まっぷたつに切り裂かれた影は、黒が薄れていきそして、水になって消えた。
気が付いたら、そこは何の変哲も無いただの部屋だった。石畳を敷き詰められた飾り気も無い殺風景な部屋。リンクが周囲を見回して、ほっとため息をつく。私もつられて安堵の息を漏らした。
「これでいいだろ、シーク」
「ああ、あとはアシナスを……」
「ばっか、お前もだよ」
リンクの声は柔らかかった。マスターソードを鞘にしまい、先にアシナスを右手で乱暴に抱えたかと思うと、反対の肩にシークを抱え込む。「ボクはもう……」「むしろ死んだ方が」そんなことをぶつぶつと呟いている彼に「シーク」アシナスは思わず呼びかけていた。気を張った、冷たい声色だと彼女は自分で思った。
「ここで死んで逃げるなんて許さない」
「何故だ……キミはボクを恨んでいたはずじゃ」
「許さない」
それはアシナスの本音だった。
死んで楽になろうなんて、許さない。死んでひとりだけ解放されようだなんて許さない。なにより――
(死んで、私から逃げようなんて許さない)
ようやく、過去の恨みも何も無く、この男に向き直れると思ったのに。こんなところでひとり逃げるなんて。
「私を傷物にした、責任を取ってもらわなきゃ困るでしょう?」
オールド・ミスだなんてまっぴらごめんだわ、なんて言うとシークは納得したようなしていないような声色で「わかった」とだけ従順に言う。シークの声に、今まで気を張っていたアシナスの全身から力が抜ける。眼球を握っていた手も緩み、ころりと零れ落ちる。
彼女の状態の変化に、話が一区切りついたのだと判断したリンクは聞き分けの無い子どもに言い聞かせるようにシークに声を掛けた。
「わかったら、シーク。旋律だ。城に帰るぞ」
両手を塞がっているリンクの状況に気が付いて、シークは頷いて何処からとも無くハープを取り出す。どこかで聞いたことがあるような厳かな音が狭い部屋に響いた。旋律が終わると同時に、三人の姿は消えていた。
その場には、ただ色の無くなった眼球のみが転がっている。
「温泉?」
城から二人の暮らす屋敷に返ってきたシークの言葉に、アシナスは思わずそう聞き返していた。左目は、眼球を王家に捧げた時から変わらず眼帯をつけているが、弄られていない右目はその青い目を大きく見開いている。だって、温泉だなんて聞きなれない言葉。それもそうだ。今までこの国にはそんなものはなかったのだから。
シークが表舞台に立って久しい――そんな彼の妻となった彼女も外交に関わってきていたのだから、外の国にはそのようなものがあることは彼女も知っていたけれど、『温泉にいかないか』だなんて言葉をこの国で、それもシークから聞くとは思いにもよらなかった。
「少し遅れたハネムーンってこと?」
ハネムーンとは、外の国の結婚に関する習慣らしい。外からの文化に触れたこの王国の民が、えらくそれを気に入ったらしく、小さなムーブメントを起こしていた――元々、蜜月を意味していたらしいこの言葉は、この国では婚姻した男女の親交を深める旅行へと意味を狭めていた。むしろ、この国の伝統では婚姻からしばらくは家から出ないことを推奨されていたのに、なんだかおかしい。
だけど、シークはいつかよりもずいぶんと柔らかくなった表情筋をふ、と緩ませながらも首を横に振った。
「違うよ。それもありだけど――それよりも、結婚の儀式の時に身体を清めなかっただろう?」
「ええ、まあ」
「それに、あんなことがあった後も結局は祈祷による払いで済ませてしまった」
あんなこと――結婚の儀式で花嫁が魔物にさらわれるという前代未聞のあの事件のことを、シークがこうやって触れるのは初めてだった。季節はあれから一回りしている。傷を癒すのにそれだけかかったのか。それとも、アシナスとシークが気を使わなくて済むほどに距離が縮まったのだろうか。後者だと嬉しい。アシナスはそう思いながらも「別にかまわないじゃないの」と素っ気ない返事をしてしまう。
「だって、あれからなにも起きてないでしょう」
「これから起きるかもしれない。それに実は、公務の一環でもあるんだ」
「どういうこと?」
「デスマウンテンの頂上、昔、大妖精の泉があったところに、温泉が沸いたそうだ」
ゴロン族はそれを売りにして観光客を呼びたいらしい。そのための協力を頼まれたんだとシークは少し気まずそうに言う。
先にそう言えばいいのに。アシナスは思ったけれどすぐに考え直す。
(でも、きっと、シークが私と一緒にいきたいと――私を気遣ってくれたのは本当なのよ)
ふふ、と思わず笑みをこぼす。
その意味をたぶん、シークは理解出来ない。それでいいのだ。それでも、彼女と彼が見合いをしたそのときよりも、近付いているのはたしかなのだから。
「そうね。行きましょう。私、ぜひ行きたい」
アシナスの屈託の無いその言葉に、シークは安心したように微笑む。これも、シークが今まで見せることの無かったものだ。シークはゼルダ以外のひとと関わることで、きっと人間になったのだ。彼を支えていた、彼に人間離れした魔力を与えていたアシナスの青い瞳はもう彼の元にはない。それでも、彼はきっと、ゼルダのことを何よりも優先するだろうけれど。
それでも、シークはアシナスを選んだのだと彼女は知っている。罪悪感からか、同上からか、それとも何か別の感情か――彼女には明確には分からないけれど、死んでしまうよりも、彼女と生きることを選んだのは間違いない。
「シーク、私、もうあなたを愛したいだなんて、絶対に言わない」
唐突なアシナスの言葉に、シークは儚くも柔らかい微笑みを浮かべたまま頷いた。歌うような声が、窓から入ってきた風に乗る。
「ボクも、キミを愛せないだなんて二度と言わない」
愛せるかどうかなんて、まだ分からない。今抱いているこの感情は愛に限りなく近い何かな気がする。だけれど、それでもまだ、この蕾みは愛になりきっていないのだ。
(そうね。『恋』から始めてみるも悪くはないわ――)
一般的に言われている、恋とも少し違うのかもしれない。だけれど、彼を見る度に心臓が変な方向に跳ねて、いろんなことを考えてしまうのは間違いない。彼に憎しみを抱いていたあの頃と同じくらい、シークのことを考えてしまう。だけど、後味がまるで違うのだ。口にすると、蜜のように甘く、毒のように繰り返し欲しくなってしまう。
「なんてことをしてくれたのよ」
結局、シークという男から、アシナスは離れられないのだ。彼を恨んでいたあの頃と、もっと違う感情が芽生えている今は同じ。結局、自分が自分ではないようなこの気持ちを味合わされるのだ。きょとんとした表情を浮かべているシークには悪いが、恨み言は、まだまだ収まりそうには無い。
The END.
愛の告白と羨望の呪詛は、何処か似ている
(⇒おまけのその後)