My Dear
数ある瞳の色の中で、『青』が特別なのは何故だろうか。
彼女に扮するための、青。
彼女と祖を同じくするのだと、そう思い込むための、青。
聖書に記されているからでもなく、それを求める者の心には『彼女』がいるのだ。
拝啓、左目に不自由したことの無いキミへ。
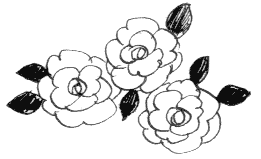
見合いから三ヶ月も立たないうちに早々と準備が整えられ、とうとう婚礼の儀が明日に迫っていた。ゼルダが我が事のように楽しそうに話を進め、衣装や会場を選び、またシークはそれに対して異存もなかったので、自分が当事者だという意識も持てないまま、ここまで来てしまった。自分は良いとしても、アシナスは気にするだろうか。元々関心の薄いシークのことよりも、ゼルダは初め彼女の心配をしていたが、彼女としても『ゼルダ様が整えてくださるなら、これに勝る喜びはありません』と返したのだと言う。
これに対して眉を寄せたのは意外にもリンクだった。ゼルダの執務室にあるソファにだらしなく腰掛け――とは言いつつ彼に隙は全くなかったのだが――ゼルダとシークを交互に見やったあと、ため息をついた。この国の人間では有り得ないだろう不遜な態度を全く気に掛けず、ゼルダはリンクに理由を問い掛けた。その時の彼のことばは、こうだ。
「シークさ。お前、そのアシナスって女のコとちゃんと会話できんの?」
「見合いの席では問題なかったように思われるけれど」
「そうじゃなくて。些細だけど、だいじな会話。お互いのこと尊重してやってけんの?」
ゼルダとともにシークがきょとんとしていると、リンクはもう一度ため息をつく。
「お前に今足りないのはさ、もっと、そういうとこなんじゃね――ま、俺ら皆に不足してると言っても過言ではないけど」
「つまり?」
「つまり、相手ときちんと対話できるのかってコト」
リンクの言うことがイマイチ理解出来なくて、疑問符を頭に浮かべてシークは首を傾げる。リンクは呆れたように目を細めた。どうしようか。悩むように二、三秒だけ間を取り、結局思ったことを告げることにしたらしい。口が開かれる。
「ゼルダの感情なんて考えずにやりたいこと押し付けてる俺が言えることじゃないけど、彼女のことちゃんと知る努力しないと、面倒が起こるぞ」
リンクはそうは言いつつも興味はなさそうに、ぼんやりと天井を眺めている。代わりに反応したのは、シークではなくゼルダだった。彼女は少し考えたような表情をしたあと、耐えるように唇を噛みしめる。
「わたくしは――あなたを選べないわたくしが、あなたを苦しめているのだと知っています」
ゼルダの静かな声が、執務室に響く。リンクは弾かれたように彼女を見て、目を見開く。ふかふかのソファに体を預けていた彼は、起きあがってゼルダの傍へ寄り、跪く。椅子に座ったままの彼女に見下ろされた状態で、そっと彼女の手をとり、手の甲に口づけを落とす。
「キミが気にすることではないよ、ゼルダ。国を選んだのなら、俺を気遣わないで。もしも、天秤が俺のほうに少しでも傾いたなら、俺はキミを奪ってしまうよ」
「……そう、ですね。でも、こうやってあなたを拘束しているわたくしが浅ましくて」
「どうせ、キミの傍にいなくたって、俺は女神サマに翻弄されるだけだって。もう一度言うよ、キミが気にすることじゃあ、ない」
リンクはグローブを外して、ゼルダに手を伸ばす。彼は、ゼルダに触れるときには必ず素手を晒すのだ。豆だらけの手。決して綺麗とは言えない戦う者の指先で、彼女の下唇をそっと撫でた。滲んでいる血に、ため息をついてリンクは指先を舐める。
「俺は好きでここに留まっているの。俺のわがままなの。だから、ゼルダ。そのことで、キミが傷つく方が本意じゃない」
まっすぐな瞳。刺すような視線に、僕ならば耐えられただろうか。シークはそう思って、そっと首を振る。自分がゼルダならば、きっと逸らしてしまったに違いない。なのに、ゼルダはリンクの強い感情から逃げることなく向き合っている。
「じゃあ、わたくしもわがままを言います。リンク、あなたは私の、そしてわたくしの民の幸せのために尽力して」
「勿論」
ああ、こういうことだと、シークは腑に落ちた気持ちだった。リンクが言いたいのはこういうことだ。婚姻の儀のことを相手と話し合えているのかと問われていたのではない。彼女の――アシナスのことを理解しようかと努めているのか、彼女と食い違ったとき、きちんと意見をすり合わせることができるのか。
「それは、わからないな」
なにせ、ゼルダ以外の人のことを、初めて眼中に入れると言っても過言ではないのだから。この先一緒にいなければならないのなら、出来る限り良好な関係を築きたい。だけど、彼女の方がそれを望んでいるかも分からないのだ。何故、彼女がシークとの結婚を了承したのか。それすらも、未だ分からない。愛せないだろうと宣言した男の元へ嫁ぐ女の気持ちは、シークには一生理解出来ないと思われた。
たしかに王家からの申し出、王家とのつながりは誰にとっても捨てがたいものであることは間違いない。だけれど、アシナスが断れるよう,配慮もあったはずだ。そこまで考えてシークは本当に、自分の見合いの事情を全く知らないことに気が付いた。王家がただで何かを行なう訳はない。ピリッとした警戒が脳を駆け抜けたが、ゼルダの手前、気が付かなかったことにする。ゼルダ自身は、きっと、シークの『シアワセ』を本当に望んでいるに違いないのだから。
その証拠に、困惑しているシークに対して、ゼルダはふわりと微笑んだ。
「少しずつ、学んでいけば良いんじゃないかしら」
ゼルダのその声が、存外柔らかかったのは、きっと彼女が喜んでいるからだろう。シークが、ゼルダの他に目を向けることを。シークの盲目的な忠誠に安堵を覚えていなかった訳はない。だけれど、彼をそうさせてしまった自分と王家の力不足を悔やんでいたのは事実だった。重荷だとは、思ったことが無い。けれど、罪悪感に押しつぶされてしまう前に、シークが『シアワセ』になる第一歩を踏み出したのだとゼルダは嬉しかった。
* * *
婚姻の儀式は、ほとんど復興しつつあるハイラル城下町の中央、噴水の前で行なわれる。
先立った婚約式はハイラル城の瞑想室にて、ごくごく身内のみを証人として行なわれた。シークの唯一の身内といっても良いゼルダが祭司となったので、シークの側にはリンクが出席をし、花嫁側としては彼女の両親の出席だった。
婚姻の儀式でも同じく、ゼルダは祭司として取り持つことになっていたので、花婿側の身内はリンクだけだった。シーカー族の男が、これほど派手に婚姻の儀を行なうのは極めて異例なことである。カカリコ村からも住人が詰め寄り、この華々しい場に居合わせた。
ハイラル城から少し離れたところ――貴族の住む高級住宅地の彼女の屋敷の前で、顔にベールを垂らしたまま、目を地面に伏せて夫となる男を待つ花嫁がいた。決して華美な装飾をしているわけではないが、王家の関係者に嫁ぐ者として恥じない、上等な絹のドレスに身を包んだアシナスは、思わずシークが息を呑む程に美しかった。
彼女を迎えるため、シークは馬車から地面に降り立つ。気配でそれを感じたのだろう、アシナスはゆっくりと顔を上げた。左目の眼帯が未だ取れていないことを、シークは酷く残念に思ったが、右の濃い黒まじりの青色だって綺麗だと素直に思う。
「……」
儀式の間、声を出してはいけないことを忘れて、呼びかけてしまうところだった。彼女の姿を捉えた瞬間から、心臓が変な方向へ自己主張している。今にもごろりと落としてしまいそうだと彼は馬鹿なことを考え、周囲に気が付かれない程度に首を横へ振った。
そっと、手を取って馬車へと導く。ドレスと同じ、真っ白い絹の手袋越しではあったが、シークは今、彼女に初めて触れた。柔らかく、きっと傷ひとつない、働かない者の手。壊してしまいそうだと思って、自分のこの考えに驚いた――壊してしまいたい、そう思ったことには気が付かない。胃の辺りがキュッと縮んで、覚えなくても良い感情が渦巻きそうだ。
自分の感情の波を統制している間に、噴水の前へと辿り着く。詰めかけていたハイラルの種族を問わない民達は、新郎新婦の乗せた馬車の通り道をあける。海を割っているような光景だった。
ゼルダの向かいに、二人揃って並び立つ。こくり、一度だけ彼女は頷いて口を大きく開いた。
「これより、婚姻の儀を執り行います」
これだけ沢山の人がいるにもかかわらず、凛としたゼルダの声が城下町全体に響き渡った。野外だがそれを物ともしない、彼女の息づかいさえ聞こえてしまいそうなほど厳粛な雰囲気だ。
ゼルダの先ほどの言葉を皮切りに、婚姻には恒例となる言葉が並べられる。韻を踏んだそれらはまるで、詩人が愛を囁くソネットのようでもあった。
町中がうっとりとしているのを、人の感情に疎いシークでもさすがに感じられるようだった。王や女王が祭司として、婚姻の儀式に出席することは限りなく稀なことだ。特に先代の王は、まず行なわなかった。だが、この女神達の国ハイラルにおいて、女王――それもゼルダと名のつく者が祭司として相応しくない訳がない。
ゼルダの読み上げが終わり、彼女は締めくくりとしてこのときに収穫した麦を両手で撒く。それはそのまま新郎新婦の上空に舞い、落ちる頃にはキラキラと七色の光になった。太陽の光と絡み合って、それは幻想的な光景を作る。シークはそれを見ながら、ふと思う。
(ああ、この儀式を使って、ゼルダはあの七年間の悪夢からの立ち直りを、民に見せたかったのかもしれない)
シークがそう結論を出したそのときだった。
新郎新婦、その関係者、そして祭司を取り囲んでいた民の壁に亀裂が入る。馬に乗った何者かがすごい勢いで、噴水の有るところに突っ込んできた。どこかで見たことが――数年前、まだハイラルが闇に包まれていた時――ゼルダとアシナスを背にかばうように、懐に隠し持っていた短刀を構えた。
「シーク!」
「分かってる!」
余裕の無い、焦った声でシークの名を呼んだリンクがぴゅううっと口笛を吹いたかと思えば、新郎新婦を運んできて近くに待機していた馬が駆け寄ってきた。「エポナ、あいつを止める」リンクが沢山の民のいるこの場から追いやるように、その者を追いつめ、城下町から出ていった。
安心している暇はない。混乱を鎮め、負傷者は救助し、無事な者は安全な場所へ誘導をしなければいけない。落ち着こうと、深呼吸をしたその瞬間、背後の噴水がザブンと音を立てて水を撒き散らした。何かが落ちてきたのか――いや、そうではない。そこには『人影』があった。実体を持っているような非常に濃い闇。リンクの面影を持つそれは、ニヤリと口元をつり上げたあとシークに黒い、マスターソードのまがい物を振りかぶる。シークの得物では、その力に圧倒されてしまう。なんとか受け流したけれど、それが精一杯。隠し持っていた毒針を投げようかとも思ったが、このような魔物に、それが通用するかは怪しかった。
リンクのいない今、ここは彼が場を収めなければならない。シークは奥歯を噛み締めて、『影』に向き直る。次の一撃に備えて、彼は構えていた。だが、その想定は外れてしまう。『影』はマスターソードを鞘にしまうと、何も持たずにシークを抜こうと走り込んできた。無防備な相手に慌てて斬り掛かる。だが、彼の胴体は水を斬ったような感触しか無い。一瞬切り裂かれたかに思えた影も、その次の刹那には元に戻っていた。化け物――その言葉が彼の中を駆け抜ける。
しかし、固まっている暇はない。その『影』がどちらを狙っているかは分からない。だが、確実に彼女達二人の娘がいる方へと走っているのだから。慌てて追いかけ、シークは無意識にゼルダを庇った。
『影』にとって、目的は彼女だったのか。それとも、どちらでもよかったのか、今となっては分からない。『影』は庇われなかった娘――アシナスを抱き込むと、そのまま本当の影になってしまったかのように、アシナスの影と同化して彼女と共に消えた。
真っ白の、絹の結婚衣装だけがその場に残される。
シン、と静まり返ったその場は、三秒か、一分か、一時間か。それとも一瞬だったのか、気が付いたときには大混乱の叫びに覆われていた。座り込んだゼルダと彼女を抱きかかえていたシークは、それでハッと我に返ったが、場を収めるのに優に一刻以上を消費してしまった。
(その眼で見る景色を、教えてはくれませんか)
<< main >>数ある瞳の色の中で、『青』が特別なのは何故だろうか。
彼女に扮するための、青。
彼女と祖を同じくするのだと、そう思い込むための、青。
聖書に記されているからでもなく、それを求める者の心には『彼女』がいるのだ。
拝啓、左目に不自由したことの無いキミへ。
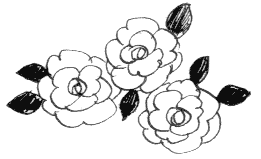
見合いから三ヶ月も立たないうちに早々と準備が整えられ、とうとう婚礼の儀が明日に迫っていた。ゼルダが我が事のように楽しそうに話を進め、衣装や会場を選び、またシークはそれに対して異存もなかったので、自分が当事者だという意識も持てないまま、ここまで来てしまった。自分は良いとしても、アシナスは気にするだろうか。元々関心の薄いシークのことよりも、ゼルダは初め彼女の心配をしていたが、彼女としても『ゼルダ様が整えてくださるなら、これに勝る喜びはありません』と返したのだと言う。
これに対して眉を寄せたのは意外にもリンクだった。ゼルダの執務室にあるソファにだらしなく腰掛け――とは言いつつ彼に隙は全くなかったのだが――ゼルダとシークを交互に見やったあと、ため息をついた。この国の人間では有り得ないだろう不遜な態度を全く気に掛けず、ゼルダはリンクに理由を問い掛けた。その時の彼のことばは、こうだ。
「シークさ。お前、そのアシナスって女のコとちゃんと会話できんの?」
「見合いの席では問題なかったように思われるけれど」
「そうじゃなくて。些細だけど、だいじな会話。お互いのこと尊重してやってけんの?」
ゼルダとともにシークがきょとんとしていると、リンクはもう一度ため息をつく。
「お前に今足りないのはさ、もっと、そういうとこなんじゃね――ま、俺ら皆に不足してると言っても過言ではないけど」
「つまり?」
「つまり、相手ときちんと対話できるのかってコト」
リンクの言うことがイマイチ理解出来なくて、疑問符を頭に浮かべてシークは首を傾げる。リンクは呆れたように目を細めた。どうしようか。悩むように二、三秒だけ間を取り、結局思ったことを告げることにしたらしい。口が開かれる。
「ゼルダの感情なんて考えずにやりたいこと押し付けてる俺が言えることじゃないけど、彼女のことちゃんと知る努力しないと、面倒が起こるぞ」
リンクはそうは言いつつも興味はなさそうに、ぼんやりと天井を眺めている。代わりに反応したのは、シークではなくゼルダだった。彼女は少し考えたような表情をしたあと、耐えるように唇を噛みしめる。
「わたくしは――あなたを選べないわたくしが、あなたを苦しめているのだと知っています」
ゼルダの静かな声が、執務室に響く。リンクは弾かれたように彼女を見て、目を見開く。ふかふかのソファに体を預けていた彼は、起きあがってゼルダの傍へ寄り、跪く。椅子に座ったままの彼女に見下ろされた状態で、そっと彼女の手をとり、手の甲に口づけを落とす。
「キミが気にすることではないよ、ゼルダ。国を選んだのなら、俺を気遣わないで。もしも、天秤が俺のほうに少しでも傾いたなら、俺はキミを奪ってしまうよ」
「……そう、ですね。でも、こうやってあなたを拘束しているわたくしが浅ましくて」
「どうせ、キミの傍にいなくたって、俺は女神サマに翻弄されるだけだって。もう一度言うよ、キミが気にすることじゃあ、ない」
リンクはグローブを外して、ゼルダに手を伸ばす。彼は、ゼルダに触れるときには必ず素手を晒すのだ。豆だらけの手。決して綺麗とは言えない戦う者の指先で、彼女の下唇をそっと撫でた。滲んでいる血に、ため息をついてリンクは指先を舐める。
「俺は好きでここに留まっているの。俺のわがままなの。だから、ゼルダ。そのことで、キミが傷つく方が本意じゃない」
まっすぐな瞳。刺すような視線に、僕ならば耐えられただろうか。シークはそう思って、そっと首を振る。自分がゼルダならば、きっと逸らしてしまったに違いない。なのに、ゼルダはリンクの強い感情から逃げることなく向き合っている。
「じゃあ、わたくしもわがままを言います。リンク、あなたは私の、そしてわたくしの民の幸せのために尽力して」
「勿論」
ああ、こういうことだと、シークは腑に落ちた気持ちだった。リンクが言いたいのはこういうことだ。婚姻の儀のことを相手と話し合えているのかと問われていたのではない。彼女の――アシナスのことを理解しようかと努めているのか、彼女と食い違ったとき、きちんと意見をすり合わせることができるのか。
「それは、わからないな」
なにせ、ゼルダ以外の人のことを、初めて眼中に入れると言っても過言ではないのだから。この先一緒にいなければならないのなら、出来る限り良好な関係を築きたい。だけど、彼女の方がそれを望んでいるかも分からないのだ。何故、彼女がシークとの結婚を了承したのか。それすらも、未だ分からない。愛せないだろうと宣言した男の元へ嫁ぐ女の気持ちは、シークには一生理解出来ないと思われた。
たしかに王家からの申し出、王家とのつながりは誰にとっても捨てがたいものであることは間違いない。だけれど、アシナスが断れるよう,配慮もあったはずだ。そこまで考えてシークは本当に、自分の見合いの事情を全く知らないことに気が付いた。王家がただで何かを行なう訳はない。ピリッとした警戒が脳を駆け抜けたが、ゼルダの手前、気が付かなかったことにする。ゼルダ自身は、きっと、シークの『シアワセ』を本当に望んでいるに違いないのだから。
その証拠に、困惑しているシークに対して、ゼルダはふわりと微笑んだ。
「少しずつ、学んでいけば良いんじゃないかしら」
ゼルダのその声が、存外柔らかかったのは、きっと彼女が喜んでいるからだろう。シークが、ゼルダの他に目を向けることを。シークの盲目的な忠誠に安堵を覚えていなかった訳はない。だけれど、彼をそうさせてしまった自分と王家の力不足を悔やんでいたのは事実だった。重荷だとは、思ったことが無い。けれど、罪悪感に押しつぶされてしまう前に、シークが『シアワセ』になる第一歩を踏み出したのだとゼルダは嬉しかった。
婚姻の儀式は、ほとんど復興しつつあるハイラル城下町の中央、噴水の前で行なわれる。
先立った婚約式はハイラル城の瞑想室にて、ごくごく身内のみを証人として行なわれた。シークの唯一の身内といっても良いゼルダが祭司となったので、シークの側にはリンクが出席をし、花嫁側としては彼女の両親の出席だった。
婚姻の儀式でも同じく、ゼルダは祭司として取り持つことになっていたので、花婿側の身内はリンクだけだった。シーカー族の男が、これほど派手に婚姻の儀を行なうのは極めて異例なことである。カカリコ村からも住人が詰め寄り、この華々しい場に居合わせた。
ハイラル城から少し離れたところ――貴族の住む高級住宅地の彼女の屋敷の前で、顔にベールを垂らしたまま、目を地面に伏せて夫となる男を待つ花嫁がいた。決して華美な装飾をしているわけではないが、王家の関係者に嫁ぐ者として恥じない、上等な絹のドレスに身を包んだアシナスは、思わずシークが息を呑む程に美しかった。
彼女を迎えるため、シークは馬車から地面に降り立つ。気配でそれを感じたのだろう、アシナスはゆっくりと顔を上げた。左目の眼帯が未だ取れていないことを、シークは酷く残念に思ったが、右の濃い黒まじりの青色だって綺麗だと素直に思う。
「……」
儀式の間、声を出してはいけないことを忘れて、呼びかけてしまうところだった。彼女の姿を捉えた瞬間から、心臓が変な方向へ自己主張している。今にもごろりと落としてしまいそうだと彼は馬鹿なことを考え、周囲に気が付かれない程度に首を横へ振った。
そっと、手を取って馬車へと導く。ドレスと同じ、真っ白い絹の手袋越しではあったが、シークは今、彼女に初めて触れた。柔らかく、きっと傷ひとつない、働かない者の手。壊してしまいそうだと思って、自分のこの考えに驚いた――壊してしまいたい、そう思ったことには気が付かない。胃の辺りがキュッと縮んで、覚えなくても良い感情が渦巻きそうだ。
自分の感情の波を統制している間に、噴水の前へと辿り着く。詰めかけていたハイラルの種族を問わない民達は、新郎新婦の乗せた馬車の通り道をあける。海を割っているような光景だった。
ゼルダの向かいに、二人揃って並び立つ。こくり、一度だけ彼女は頷いて口を大きく開いた。
「これより、婚姻の儀を執り行います」
これだけ沢山の人がいるにもかかわらず、凛としたゼルダの声が城下町全体に響き渡った。野外だがそれを物ともしない、彼女の息づかいさえ聞こえてしまいそうなほど厳粛な雰囲気だ。
ゼルダの先ほどの言葉を皮切りに、婚姻には恒例となる言葉が並べられる。韻を踏んだそれらはまるで、詩人が愛を囁くソネットのようでもあった。
町中がうっとりとしているのを、人の感情に疎いシークでもさすがに感じられるようだった。王や女王が祭司として、婚姻の儀式に出席することは限りなく稀なことだ。特に先代の王は、まず行なわなかった。だが、この女神達の国ハイラルにおいて、女王――それもゼルダと名のつく者が祭司として相応しくない訳がない。
ゼルダの読み上げが終わり、彼女は締めくくりとしてこのときに収穫した麦を両手で撒く。それはそのまま新郎新婦の上空に舞い、落ちる頃にはキラキラと七色の光になった。太陽の光と絡み合って、それは幻想的な光景を作る。シークはそれを見ながら、ふと思う。
(ああ、この儀式を使って、ゼルダはあの七年間の悪夢からの立ち直りを、民に見せたかったのかもしれない)
シークがそう結論を出したそのときだった。
新郎新婦、その関係者、そして祭司を取り囲んでいた民の壁に亀裂が入る。馬に乗った何者かがすごい勢いで、噴水の有るところに突っ込んできた。どこかで見たことが――数年前、まだハイラルが闇に包まれていた時――ゼルダとアシナスを背にかばうように、懐に隠し持っていた短刀を構えた。
「シーク!」
「分かってる!」
余裕の無い、焦った声でシークの名を呼んだリンクがぴゅううっと口笛を吹いたかと思えば、新郎新婦を運んできて近くに待機していた馬が駆け寄ってきた。「エポナ、あいつを止める」リンクが沢山の民のいるこの場から追いやるように、その者を追いつめ、城下町から出ていった。
安心している暇はない。混乱を鎮め、負傷者は救助し、無事な者は安全な場所へ誘導をしなければいけない。落ち着こうと、深呼吸をしたその瞬間、背後の噴水がザブンと音を立てて水を撒き散らした。何かが落ちてきたのか――いや、そうではない。そこには『人影』があった。実体を持っているような非常に濃い闇。リンクの面影を持つそれは、ニヤリと口元をつり上げたあとシークに黒い、マスターソードのまがい物を振りかぶる。シークの得物では、その力に圧倒されてしまう。なんとか受け流したけれど、それが精一杯。隠し持っていた毒針を投げようかとも思ったが、このような魔物に、それが通用するかは怪しかった。
リンクのいない今、ここは彼が場を収めなければならない。シークは奥歯を噛み締めて、『影』に向き直る。次の一撃に備えて、彼は構えていた。だが、その想定は外れてしまう。『影』はマスターソードを鞘にしまうと、何も持たずにシークを抜こうと走り込んできた。無防備な相手に慌てて斬り掛かる。だが、彼の胴体は水を斬ったような感触しか無い。一瞬切り裂かれたかに思えた影も、その次の刹那には元に戻っていた。化け物――その言葉が彼の中を駆け抜ける。
しかし、固まっている暇はない。その『影』がどちらを狙っているかは分からない。だが、確実に彼女達二人の娘がいる方へと走っているのだから。慌てて追いかけ、シークは無意識にゼルダを庇った。
『影』にとって、目的は彼女だったのか。それとも、どちらでもよかったのか、今となっては分からない。『影』は庇われなかった娘――アシナスを抱き込むと、そのまま本当の影になってしまったかのように、アシナスの影と同化して彼女と共に消えた。
真っ白の、絹の結婚衣装だけがその場に残される。
シン、と静まり返ったその場は、三秒か、一分か、一時間か。それとも一瞬だったのか、気が付いたときには大混乱の叫びに覆われていた。座り込んだゼルダと彼女を抱きかかえていたシークは、それでハッと我に返ったが、場を収めるのに優に一刻以上を消費してしまった。
女王の狗
(その眼で見る景色を、教えてはくれませんか)