My Dear
『青い瞳は魔力を持つ』
古来そのうつくしさ故に、青い瞳が求められていたわけではない。
青い瞳は、魔力の持つ加護の証しだったのだ。
拝啓、左目に不自由したことの無いキミへ。
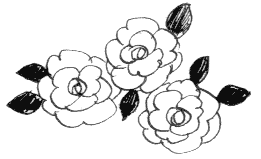
ゼルダのことは守れたものの、よりにもよって自分の花嫁を目の前で攫われたシークは、帰ってきたリンクにぶん殴られることになった。
それを当然のこととして受け入れたシークに、リンクは何故か余計に憤ったようにクソ、と地面に悪態を吐き捨てる。
「……謝らなければならないのは俺の方だって、わかってんだよ。シーク。しくじったのは俺だから。まさか、ダークリンクまで」
「ダークリンクというのですか」
シークが自分を庇ったせいで、アシナスが攫われたのだと、こちらも責任を感じて黙り込んでいたゼルダがそっと口を開いた。リンクはそれに反応して、そっと首を振る。「本当のところは、分からない。それも、ナヴィが勝手に名付けた名前だから」やはり、あの七年間の遺産だったのか。シークは思わず納得してしまう。
「リンクは、この事態を想定していたのか」
「ああ……きっとこの華々しい、ハイラル王家の復活を示すような事態に、残党は必ず現れるだろうと思ってた」
「だから、シークに見合いを薦めてきたんですね」
「そう。囮に使ったみたいで悪かった、シーク」
ゼルダの治めるこの地に不安要素を置いておきたくなかったが故のこの行動だろう。しかし今、リンクは寄りにもよって守りたかったゼルダによって断罪を受けていた。
シークが咎めることじゃない。普通ならば殴り返しても良い状況なのに、シークは怒る気すらしなかった。守れなかったのは、シークの力不足故。何が、宮廷騎士だ。何が、近衛隊だ。何が、シーカー族だ。力も無く、ゼルダにまで責任を感じさせて、シークはこれまでに無い程自分に憤りを感じていた。
「ここに戻ってきたってことは、居場所を掴んだんだろう? リンク」
シークの静かな問いかけに、リンクはコクリと頷いた。「水の神殿だよ」賢者達が守りに就いてから、一度も開かれたことの無いはずのその神殿達。そこへどうやって入ったというのだろう。
「ダークリンクは、自分の印をつけた影に移動が出来るらしいんだ――そして、水の神殿は奴の最も身近な場所だ」
一度、そこで死を向かえたはずでもある。トドメをさせていなかったのだろうか――リンクが心の中に浮かんだ疑問をそっと握りつぶして、シークに向き直る。
「奴はきっと俺しか倒せない。だから、俺が行く。だけどその時、周囲に気を配っている余裕は無いと思う。シーク、キミに着いて来てもらいたいんだ。着いてきて、俺からあの人質の女のコを守って欲しい」
「言われなくてもそのつもりだったよ、リンク。これは、ボクの失態でもある。あの子はボクが守らなきゃいけなかったんだから」
「悪かった」
淡々とした、感情を感じさせないシークの声に、リンクは思わず謝罪を口にしていた。だが、シークは首を横に振ってそれを否定する。
「責めてる訳でも皮肉を言ってる訳でもないさ。ああ、でも」
「?」
「ボクに、キミの相棒は務まるかな?」
これが、シークの精一杯の冗談だったんだろう。場を馴染ませようとするそれに、リンクは無理にぎこちない笑みを作って頷いた。
「きっと、大丈夫さ」
その二人の様子を見て、ゼルダはホッとしたように弱々しく微笑む。きっとこの二人ならなんとかしてくれるに違いない――身体の芯に根付いた無意識の信頼が、彼女の微笑みを引き出したのだ。
* * *
水の神殿に入るまでは、簡単だった。シークはリンクとともに移動旋律を用いてハイリア湖畔まで向かい、湖に沈む。シークはシーカー族の民族衣装を着込んで魔法を用い(シーカー族の衣装の方が魔法の効き目が良い気がして、しばしばシークはこの衣装を着ることがある)、リンクはゾーラの服を着込んでいるため、水中でも呼吸の心配はない。古代、婚姻の儀では神聖なる妖精の泉に新郎新婦は身を浸して清めたという。その行程を抜かしたから、このような目にあっているのか。そんなことさえ考えてしまう。
(らしくないな)
自分で自分のことを笑って、シークはリンクに着いていった。神殿の中の構造は自分よりも、リンクの方が詳しい。リンクだってか弱い少女ならともかく同じ仲間と認めているシークに気を使うでも無くすたすたと先を歩く。複雑な神殿内部に迷いそうになりながらも、ようやく二人は過去、リンクがダークリンクと剣を交えたその部屋へ辿り着いた。
「ダーク。俺が来たよ」
リンクは部屋へ入り、開口一番そう言った。
誰の姿も見えないその部屋――というよりも何も無い水の滴る平原のように見えた――に向かって、大声を出すのは何だかおかしかった。リンクの声は反響して何重にも響き渡る。そのおかげで、見た目に反して部屋が狭いのだと――やはりここは部屋なのだと分かった。
反応がないので、リンクは肩をすくめながら中央へゆっくりと歩みを進める。シークはここで待ってて。そう言うように、着いていこうとしたシークに右の手のひらを向けた。
「今度の目的は何だい、ダークリンク。キミのご主人様はもう――」
「リンク、影が!」
「え?」
リンクが丁度、空間の真ん中辺りに辿り着いた頃、彼には《無いはず》の影がにゅぅっと現れた。すっと色濃くなっていくそれに、シークが思わず声を上げる。
その影を扉とでもするかのように、『影』の魔物は現れた。地面から突然生えてきたような闇色の『影』は、左手にぐったりとした花嫁姿の娘を抱え、右手に聖剣のまがい物を握っていた。
リンクの疑問の声と同時に、その剣は振りかぶられる。間一髪、リンクの反射的な防御のおかげで傷を負うことは無かったようだ。『影』は気に障ったように舌打ちをして、左手に抱えていた娘を投げ捨てる。(――アシナス!)叫びたい気持ちを何故かグッと堪え、黙ったまま彼女の元へ走った。
「ゴタゴタとうるせえ奴だな。あの相棒がいなくなった分、てめぇが喋るってぇのかい」
現在、『影』の関心はあくまでリンクにあるらしい。
シークが彼女に駆け寄ったところで、なんら反応を示すことはなかった。おかげでシークは彼女を、もし彼らが戦闘を開始してもすぐには被害の及ばない場所へ彼女を移動させ、様子を確認することが出来た。
長い髪の毛は泥水に浸ったような汚れやぐちゃぐちゃに動かされたような乱れがあるが、大きく変わったところは無い。衣装も同じだ、真っ白衣装はあっさりとよごれに染まっているものの、深紅の染みも無ければ、切り裂かれた様子も無い。もちろん衣装の下も同じだ。
シークはホッとして彼女の表情を伺うべく、顔に目を向けた。そこで思わず愕然としてしまう。彼女の左目にあったはずの眼帯は外れていた。瞼は閉じていたが、その下にはまるで何も無いかのようだった。あるはずの膨らみは無く、瞼は空洞へと下がっている。捲ったところで、あるはずの眼球は――ゼルダが褒めたたえていた美しい瞳は無いのだろう。
「アシナス、その瞳は……! もしかして、」
『影』に抉られたのだろうか、そう問いかけようとしたら「気にしないで良いの、シーク」弱々しい彼女の声に遮られた。気にしない訳にはいかないではないか! 自分は、あれほどまでに彼女の瞳を見ることを楽しみにしていたのに――楽しみに、待ち望んでいた自分を、シークはここで初めて自覚した。
シークの憤りに答えたのは、アシナスではなかった。彼女は息も絶え絶えに何かを言おうとしていたが、聞き取ることが出来ない。そのうちに、リンクとやり合っていた『影』の魔物が視線はそのままリンクから外さずに、シーク言い放った。
「おいおい、冗談だろう。その女の眼は、よりにもよってシーカー族のガキに捧げられたって話じゃないか。しらばっくれんなよ、シーカー族。まずはこの勇者気取りをぶっ殺してから相手にしてやっからよ」
「シーカー族の、子どもに……?」
いつの話だ。
いつの話だ、それは。
心当たりが無い訳ではない。むしろ有りすぎるくらいだ。
シーカー族の子どもだった自分が、どこからともなく、この魔法の青い瞳を与えられたのは。ゼルダに扮するため。ゼルダの影武者として。紅い瞳の左側を抉られて、埋め込まれた。どうして疑問に持たなかったのだろう。今のハイラルには、義眼を作る技術などないと言うのに。どうして気が付かなかったのだろう――アシナスの眼球は、疾うに空っぽだったということに。
「シーク、気にしちゃだめよ」
私はもう充分、あなたを恨んだのだから。囁き声が、そう言った。
シークは呆然と、その場に立ち尽くす。指先の力が上手く入らなくて、握っていた短刀が危な気にその場に落ちて、二、三度跳ねた。
「……なんだ、なるほど。お前が今の持ち主か」
ニヤ、と何が楽しいのか『影』は口元を歪ませて、リンクとの戦いから離脱しシークの元へと駆けてくる。
「シーク! 逃げろ!!」
リンクのその声が耳に入って、そのまま抜けていく。動けない。『影』の方がリンクよりも早くシークの元へと辿り着いた。『影』はいつもグローブをつけているリンクとは違い、剥き出しの、とんがった爪を、シークに向けた。そこでようやく抵抗らしい抵抗を始めるシークだったが、間に合わない。単純な力比べだと、圧倒的に魔物の方が強い。「シーク!」リンクとアシナスの声が重なって、部屋に反響する。
その次の刹那には『影』の爪先が、左目に収容されていた青い眼球をえぐり出す。『影』の手の中にはおとなしく収まらず、そのまま手鞠のように跳ねて、転がった。
今までの任務で、どんな痛みにも根を上げることの無かったシークの絶叫を背景に、『影』とリンクと、そして横たわっていた少女がそれぞれ剥き出しの青い瞳の眼球に手を伸ばす。
ほとんど、同じタイミングだと思われた。
その中でも、一番早くそれを手にしたのは、真っ白い働かない手だった。
元の持ち主――アシナスのものだった。
(もう恨んでなんかいないから、どうかご無事で)
<< main >>『青い瞳は魔力を持つ』
古来そのうつくしさ故に、青い瞳が求められていたわけではない。
青い瞳は、魔力の持つ加護の証しだったのだ。
拝啓、左目に不自由したことの無いキミへ。
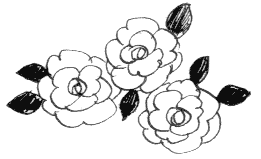
ゼルダのことは守れたものの、よりにもよって自分の花嫁を目の前で攫われたシークは、帰ってきたリンクにぶん殴られることになった。
それを当然のこととして受け入れたシークに、リンクは何故か余計に憤ったようにクソ、と地面に悪態を吐き捨てる。
「……謝らなければならないのは俺の方だって、わかってんだよ。シーク。しくじったのは俺だから。まさか、ダークリンクまで」
「ダークリンクというのですか」
シークが自分を庇ったせいで、アシナスが攫われたのだと、こちらも責任を感じて黙り込んでいたゼルダがそっと口を開いた。リンクはそれに反応して、そっと首を振る。「本当のところは、分からない。それも、ナヴィが勝手に名付けた名前だから」やはり、あの七年間の遺産だったのか。シークは思わず納得してしまう。
「リンクは、この事態を想定していたのか」
「ああ……きっとこの華々しい、ハイラル王家の復活を示すような事態に、残党は必ず現れるだろうと思ってた」
「だから、シークに見合いを薦めてきたんですね」
「そう。囮に使ったみたいで悪かった、シーク」
ゼルダの治めるこの地に不安要素を置いておきたくなかったが故のこの行動だろう。しかし今、リンクは寄りにもよって守りたかったゼルダによって断罪を受けていた。
シークが咎めることじゃない。普通ならば殴り返しても良い状況なのに、シークは怒る気すらしなかった。守れなかったのは、シークの力不足故。何が、宮廷騎士だ。何が、近衛隊だ。何が、シーカー族だ。力も無く、ゼルダにまで責任を感じさせて、シークはこれまでに無い程自分に憤りを感じていた。
「ここに戻ってきたってことは、居場所を掴んだんだろう? リンク」
シークの静かな問いかけに、リンクはコクリと頷いた。「水の神殿だよ」賢者達が守りに就いてから、一度も開かれたことの無いはずのその神殿達。そこへどうやって入ったというのだろう。
「ダークリンクは、自分の印をつけた影に移動が出来るらしいんだ――そして、水の神殿は奴の最も身近な場所だ」
一度、そこで死を向かえたはずでもある。トドメをさせていなかったのだろうか――リンクが心の中に浮かんだ疑問をそっと握りつぶして、シークに向き直る。
「奴はきっと俺しか倒せない。だから、俺が行く。だけどその時、周囲に気を配っている余裕は無いと思う。シーク、キミに着いて来てもらいたいんだ。着いてきて、俺からあの人質の女のコを守って欲しい」
「言われなくてもそのつもりだったよ、リンク。これは、ボクの失態でもある。あの子はボクが守らなきゃいけなかったんだから」
「悪かった」
淡々とした、感情を感じさせないシークの声に、リンクは思わず謝罪を口にしていた。だが、シークは首を横に振ってそれを否定する。
「責めてる訳でも皮肉を言ってる訳でもないさ。ああ、でも」
「?」
「ボクに、キミの相棒は務まるかな?」
これが、シークの精一杯の冗談だったんだろう。場を馴染ませようとするそれに、リンクは無理にぎこちない笑みを作って頷いた。
「きっと、大丈夫さ」
その二人の様子を見て、ゼルダはホッとしたように弱々しく微笑む。きっとこの二人ならなんとかしてくれるに違いない――身体の芯に根付いた無意識の信頼が、彼女の微笑みを引き出したのだ。
水の神殿に入るまでは、簡単だった。シークはリンクとともに移動旋律を用いてハイリア湖畔まで向かい、湖に沈む。シークはシーカー族の民族衣装を着込んで魔法を用い(シーカー族の衣装の方が魔法の効き目が良い気がして、しばしばシークはこの衣装を着ることがある)、リンクはゾーラの服を着込んでいるため、水中でも呼吸の心配はない。古代、婚姻の儀では神聖なる妖精の泉に新郎新婦は身を浸して清めたという。その行程を抜かしたから、このような目にあっているのか。そんなことさえ考えてしまう。
(らしくないな)
自分で自分のことを笑って、シークはリンクに着いていった。神殿の中の構造は自分よりも、リンクの方が詳しい。リンクだってか弱い少女ならともかく同じ仲間と認めているシークに気を使うでも無くすたすたと先を歩く。複雑な神殿内部に迷いそうになりながらも、ようやく二人は過去、リンクがダークリンクと剣を交えたその部屋へ辿り着いた。
「ダーク。俺が来たよ」
リンクは部屋へ入り、開口一番そう言った。
誰の姿も見えないその部屋――というよりも何も無い水の滴る平原のように見えた――に向かって、大声を出すのは何だかおかしかった。リンクの声は反響して何重にも響き渡る。そのおかげで、見た目に反して部屋が狭いのだと――やはりここは部屋なのだと分かった。
反応がないので、リンクは肩をすくめながら中央へゆっくりと歩みを進める。シークはここで待ってて。そう言うように、着いていこうとしたシークに右の手のひらを向けた。
「今度の目的は何だい、ダークリンク。キミのご主人様はもう――」
「リンク、影が!」
「え?」
リンクが丁度、空間の真ん中辺りに辿り着いた頃、彼には《無いはず》の影がにゅぅっと現れた。すっと色濃くなっていくそれに、シークが思わず声を上げる。
その影を扉とでもするかのように、『影』の魔物は現れた。地面から突然生えてきたような闇色の『影』は、左手にぐったりとした花嫁姿の娘を抱え、右手に聖剣のまがい物を握っていた。
リンクの疑問の声と同時に、その剣は振りかぶられる。間一髪、リンクの反射的な防御のおかげで傷を負うことは無かったようだ。『影』は気に障ったように舌打ちをして、左手に抱えていた娘を投げ捨てる。(――アシナス!)叫びたい気持ちを何故かグッと堪え、黙ったまま彼女の元へ走った。
「ゴタゴタとうるせえ奴だな。あの相棒がいなくなった分、てめぇが喋るってぇのかい」
現在、『影』の関心はあくまでリンクにあるらしい。
シークが彼女に駆け寄ったところで、なんら反応を示すことはなかった。おかげでシークは彼女を、もし彼らが戦闘を開始してもすぐには被害の及ばない場所へ彼女を移動させ、様子を確認することが出来た。
長い髪の毛は泥水に浸ったような汚れやぐちゃぐちゃに動かされたような乱れがあるが、大きく変わったところは無い。衣装も同じだ、真っ白衣装はあっさりとよごれに染まっているものの、深紅の染みも無ければ、切り裂かれた様子も無い。もちろん衣装の下も同じだ。
シークはホッとして彼女の表情を伺うべく、顔に目を向けた。そこで思わず愕然としてしまう。彼女の左目にあったはずの眼帯は外れていた。瞼は閉じていたが、その下にはまるで何も無いかのようだった。あるはずの膨らみは無く、瞼は空洞へと下がっている。捲ったところで、あるはずの眼球は――ゼルダが褒めたたえていた美しい瞳は無いのだろう。
「アシナス、その瞳は……! もしかして、」
『影』に抉られたのだろうか、そう問いかけようとしたら「気にしないで良いの、シーク」弱々しい彼女の声に遮られた。気にしない訳にはいかないではないか! 自分は、あれほどまでに彼女の瞳を見ることを楽しみにしていたのに――楽しみに、待ち望んでいた自分を、シークはここで初めて自覚した。
シークの憤りに答えたのは、アシナスではなかった。彼女は息も絶え絶えに何かを言おうとしていたが、聞き取ることが出来ない。そのうちに、リンクとやり合っていた『影』の魔物が視線はそのままリンクから外さずに、シーク言い放った。
「おいおい、冗談だろう。その女の眼は、よりにもよってシーカー族のガキに捧げられたって話じゃないか。しらばっくれんなよ、シーカー族。まずはこの勇者気取りをぶっ殺してから相手にしてやっからよ」
「シーカー族の、子どもに……?」
いつの話だ。
いつの話だ、それは。
心当たりが無い訳ではない。むしろ有りすぎるくらいだ。
シーカー族の子どもだった自分が、どこからともなく、この魔法の青い瞳を与えられたのは。ゼルダに扮するため。ゼルダの影武者として。紅い瞳の左側を抉られて、埋め込まれた。どうして疑問に持たなかったのだろう。今のハイラルには、義眼を作る技術などないと言うのに。どうして気が付かなかったのだろう――アシナスの眼球は、疾うに空っぽだったということに。
「シーク、気にしちゃだめよ」
私はもう充分、あなたを恨んだのだから。囁き声が、そう言った。
シークは呆然と、その場に立ち尽くす。指先の力が上手く入らなくて、握っていた短刀が危な気にその場に落ちて、二、三度跳ねた。
「……なんだ、なるほど。お前が今の持ち主か」
ニヤ、と何が楽しいのか『影』は口元を歪ませて、リンクとの戦いから離脱しシークの元へと駆けてくる。
「シーク! 逃げろ!!」
リンクのその声が耳に入って、そのまま抜けていく。動けない。『影』の方がリンクよりも早くシークの元へと辿り着いた。『影』はいつもグローブをつけているリンクとは違い、剥き出しの、とんがった爪を、シークに向けた。そこでようやく抵抗らしい抵抗を始めるシークだったが、間に合わない。単純な力比べだと、圧倒的に魔物の方が強い。「シーク!」リンクとアシナスの声が重なって、部屋に反響する。
その次の刹那には『影』の爪先が、左目に収容されていた青い眼球をえぐり出す。『影』の手の中にはおとなしく収まらず、そのまま手鞠のように跳ねて、転がった。
今までの任務で、どんな痛みにも根を上げることの無かったシークの絶叫を背景に、『影』とリンクと、そして横たわっていた少女がそれぞれ剥き出しの青い瞳の眼球に手を伸ばす。
ほとんど、同じタイミングだと思われた。
その中でも、一番早くそれを手にしたのは、真っ白い働かない手だった。
元の持ち主――アシナスのものだった。
シーカー族の少年
(もう恨んでなんかいないから、どうかご無事で)